
-
位牌
-
位牌とは|仏壇があれば位牌は必要ない?

故人さまの位牌を取り扱う場合、魂入れと魂抜きが必要です。
適切に魂入れと魂抜きしないと、位牌はただの板と認識され、供養の対象とならないと考えられているため、注意が必要となるでしょう。
また、お坊さんや菩提寺(ぼだいじ)から故人さまの供養が不十分と捉えられ、後の関係に影響を及ぼすこともあるのではないでしょうか。
この記事では、位牌の魂入れ・魂抜きは必要ないか、タイミング、注意点、移動させて良いものか、チェックポイント、ダメな例、正しいマナー、正しい置き方・並べ方について詳しく解説します。
位牌の魂入れ・魂抜きが必要ないか気になる人は、ぜひご参考ください。



故人さまの位牌の魂入れや魂抜きが必要かどうかは、ご遺族や喪主の考え方によって変わるため、身内で話し合って決めるべきです。
ここでは、位牌の魂入れ・魂抜きは必要ないかについて詳しく解説します。
そもそも位牌の魂入れとは、新たに購入した位牌に故人さまの魂を宿らせる儀式のことです。
通常、位牌は何もしなければただの木製の板ですが、魂入れを行うことによって、故人さまに対して祈る場所もしくは故人さまを祀る場所として意味を持つようになります。
つまり、故人さまを常に感じられるよう、位牌に魂を宿す行為が魂入れといえるでしょう。
似たような言葉に魂抜きという言葉がありますが、魂抜きは故人さまの位牌を移動させたり処分したりするときに、その位牌から魂を抜く儀式のことをいいます。
普通、位牌に一度故人さまの魂を宿らせた場合、そのまま移動や処分はできません。
故人さまの魂が宿っている状態であるため、一度魂抜きの儀式を行い、適切に故人さまの魂を抜いてから動かしたり捨てたりする必要があります。
魂入れも魂抜きも、位牌を扱う場合に必要となる儀式です。
おさらいになりますが、故人の魂を位牌に宿すことを魂入れ、抜くことを魂抜きと呼びます。
位牌は何もしなければただの木製の板であり、故人さまの魂が宿っていない状態と認識されるため、仏壇などに置く場合には魂入れや魂抜きが必要です。
新たに購入する場合は魂入れ、移動や処分を行う場合は魂抜きが必要となります。
仏教においては魂入れも魂抜きも必要と考えられるため、もしどのように対応すれば良いかわからない場合は、お世話になっているお坊さんや菩提寺に聞いてみましょう。
なお、以下の記事では仏壇を買った後に必要な開眼供養、仏壇を手放す場合に必要な手続きについて詳しく解説しているため、あわせて参考にしてみてください。
こちらの記事を読んでいる方におすすめ こちらの記事を読んでいる方におすすめ

魂入れや魂抜きをしない場合、以下のような問題が発生します。
魂入れをしない場合、お坊さんや菩提寺との関係に影響が出たり、故人さまの供養の対象にならなかったりと、何かと問題となります。
また、魂抜きをしなかった場合、移動や処分の際に宗教的なマナー違反となったり、故人さまの魂を傷つけることになったりと、同じく問題になりやすいです。
以上のことから位牌を取り扱う場合、魂入れや魂抜きは必須といえるのではないでしょうか。

位牌の魂入れと魂抜きのタイミングは、以下の通りです。
主に、魂入れは新たに位牌を購入したとき、魂抜きは位牌を移動させたり処分したりするときに必要となります。タイミングは魂入れが先、魂抜きが後となるため、順序に注意が必要です。
なお、初めて身内がお亡くなりになり、位牌をどうすれば良いかわからない場合は、お世話になっているお坊さんや菩提寺に尋ねると良いでしょう。
順番的には魂入れが先、魂抜きが後とはなりますが、タイミングに厳密な決まりはなく、家庭や地域によっても独自の決まりが設けられている場合があるため、適宜確認が求められます。
地元の葬儀社や年長者に聞いてみるのも、良いのではないでしょうか。

位牌の魂入れと魂抜きでは、いくつか注意が必要です。
ここでは、位牌の魂入れ・魂抜きの注意点について詳しく解説します。
位牌の魂入れや魂抜きといった宗教的な儀式に関しては、お坊さんもしくは菩提寺に対するお布施やお車代が必要となります。
具体的にいくら必要なのかは関係性によって変わる他、家庭や地域によっても変わるため具体的な金額は明示できませんが、どちらも現金で支払うのがマナーです。
位牌の設置と同時に四十九日法要を行う場合は、法要のお布施もまとめてお渡しすると良いでしょう。
なお、お食事をされる場合は別途御膳料も必要となります。
お布施やお車代、御膳料はあくまでも気持ちであるため、原則いくらでも構いません。あまりにも常識から逸脱する金額はマナー違反ですが、数千円〜数万円の範囲であれば差し支えはありません。
当然ながら、魂入れや魂抜きをしない選択をした場合はお布施なしでも大丈夫です。
念のため、お坊さんや菩提寺に許可を取り、双方の関係性に配慮してからどうするのかを判断すると良いのではないでしょうか。
位牌の魂入れや魂抜きは、お世話になっている菩提寺のお坊さんに依頼することになるため、あらかじめ予定をご確認ください。
いきなり今日明日必要といっても、お坊さんによっては他の予定が入っています。
お葬式以外にもお坊さんはさまざまな予定があり、タイミングが合わないことも珍しくないため、余裕を持って頼んでおくと安心です。
土日祝日をまたぐ場合は、事前に連絡しておきましょう。
位牌の魂入れや魂抜きは、宗教や宗派によっては不要となります。
例えば、浄土真宗では魂が存在するという考え方をしないため、そもそも位牌に魂入れや魂抜きを行う必要がありません。
他にも、日本には同じ宗教でも宗派によって考え方が変わる場合があるため、故人さまが何を信仰していたのか、一度確認しておくと安心です。
位牌の取り扱いについては、仏具店にご相談ください。
初めて位牌を購入する場合、わからないことの方が多いです。魂入れや魂抜きについても、故人さまがお亡くなりになって初めて知ったという人も少なくないと思います。
位牌をはじめ、仏壇などの取り扱いは初めてだとわからないことだらけなため、一度仏具店に直接出向いて疑問点を解決しておきましょう。
仏具店によっては位牌の正しい扱い方について教えてくれるところもあるため、わからないことは専門のスタッフに相談しておくのが望ましいです。
なお、最近では永代供養などの観点から位牌を購入しない家庭も珍しくないため、仏壇を置くかどうかを含め身内で一度話し合っておくことが推奨されます。

位牌を移動させる場合、そもそも移動させて良いのか迷う人もいるはずです。
ここでは、位牌は移動させても良いものかについて詳しく解説します。
きちんとした作法にしたがって行えば、位牌を移動させること自体はNGな行為ではありません。ルールを守って移動をする限りは、特に問題になることはありませんので、万が一、位牌を動かさなければならなくなったときにも余り神経質になる必要はありません。
故人を供養する上でも、位牌は常に目の届くところに安置しておく方がよいでしょう。
位牌を移動する際には、実のところいろいろなルールがあります。
特に注意をしたいのが、位牌を家の外に持ち出すケースです。こういったケースの場合は、少しルールが複雑になってくるため、注意が必要になるでしょう。
家の中で別室に位牌を移動するときなどは、できるだけ丁重に扱えば、通常通り持ち歩いてもさして問題はないでしょう。仏壇の中に位牌を安置している場合は、仏壇ごと移動します。 住宅事情等で仏壇を動かすことができず、位牌だけを取り出して他の部屋に移す場合、位牌を安置する小さめの厨子はあった方が良いでしょう。
掃除など一時的な理由で仏壇から位牌を動かす程度であれば、丁寧に扱えば特に問題はありません。
位牌を家から持ち出す場合、基本的にはあらためて魂抜きや魂入れなどをする必要はありません。
ただし、別の場所に移動する区切りとして、場合によっては新しい場所でお迎えするための儀式を行うことはあります。迷ったら菩提寺などに確認を取っておくと安心でしょう。
家の建て替えなどの際には、仏壇ごと移動することが多いですが、このようなときにもしかるべき方法にそって行う必要があり、適当に移動するのはご法度です。
こちらの記事を読んでいる方におすすめ

位牌を移動させる場合は、いくつかのチェックポイントを知っておくと安心です。
ここでは、位牌を移動させる前のチェックポイントについて詳しく解説します。
宗教や宗派によって、位牌を移動させる際のルールが変わるため、注意が必要です。
浄土真宗のように故人さまの魂が存在するという考え方をしない場合は、移動に際して魂入れや魂抜きを行う必要はありません。一般的な仏教の場合は必要です。
お坊さんや菩提寺によっても考え方が変わる場合があるため、不安な場合は普段からお世話になっているお坊さんもしくは菩提寺に正しいルールをご確認ください。
仏壇がある場合とない場合で、基本的に位牌の移動の仕方が変わります。
例えば、仏壇がある場合は仏壇ごと位牌を移動させるのですが、仏壇がない場合は位牌のみを移動させることになるため、各方法に応じて準備が必要です。
永代供養などで位牌も仏壇も設置しない場合は、また別の手段で供養することになるため、故人さまがお亡くなりになった段階で一度ご家族やご親族に相談しておきましょう。

位牌を移動させる場合、ダメな例があるため、勝手に動かす前に確認が必要です。
ここでは、位牌を移動させる場合のダメな例について詳しく解説します。
魂抜きなしで位牌を動かすのは、NGです。
魂入れを行った位牌には故人さまの魂が宿っていると考えるため、魂抜きなしで位牌を動かすのは故人さまのためにも避けるべきとされます。
何かしらの理由で位牌を動かす場合は、魂抜きをしてから移動させてください。
仏壇を横にして運ぶのは、当然ながらNGとなります。故人さまを祀るための仏壇は大切なものとされるため、横にするのは宗教的にマナー違反です。
横にして持ち運ぶと壊れたり倒れたりする可能性もあるため、縦にして持ち運びましょう。
他人に仏壇を運ばせるのも、もちろんNGです。故人さまと生前に関係のあった人もしくは知人であれば問題ないのですが、赤の他人が運ぶのは宗教的にマナー違反となります。
例外として仏具店のスタッフなどは運んでも問題ないため、自分で運べそうもない場合はプロにご依頼ください。
魂入れをせずに位牌を飾ることも、NGとされています。
厳密には魂入れを行わずに位牌を飾ることはできるのですが、仏教の世界では魂入れをすることで位牌に故人さまの魂が宿ると考えるのが通例です。
特別な理由がない限り、位牌を飾る際には魂入れを行いましょう。

位牌を移動させる場合、宗教的なマナーを守ることが重要です。
ここでは、位牌を移動させるときの正しいマナーについて詳しく解説します。
位牌を仏壇の中に安置している場合は、仏壇ごと移動させます。
この場合、魂抜きの法要が必要になってくるため、1ヵ月ほど前には寺に連絡を入れておきたいところです。
仏壇、位牌の魂抜きをしてもらえば、後はスムーズに移動ができます。一旦魂抜きが終わったら、仏壇は引っ越し業者に運んでもらっても問題はありません。位牌や本尊は、風呂敷などに包んで自分で運びましょう。
新しい場所に仏壇、位牌を設置したら、忘れずに魂入れの法要を行います。
仏壇を特に設置していない場合は魂抜きなども特に不要で、位牌を自分の手に持って運ぶことができます。ただ、このようなときにも、位牌をそのまま裸の状態で運ぶのは考えものです。
日本では大切なものは包んで持ち運ぶ習慣がありますので、風呂敷などにくるんで丁寧に持ち運びます。
標準サイズの位牌を包むときには、68センチ前後の風呂敷を使うと便利です。こういった風呂敷にくるむことで、持ち運びの最中に位牌の表面に傷が付くのを避けられます。
仏壇を処分して、中に安置されている位牌のみを移動したい場合は、仏壇の魂抜きとお焚き上げの儀式をすることが必要です。
魂抜きやお焚き上げは、古い仏壇を処分するときなどに行われる儀式。魂を抜くことで、物として仏壇を処分できるようになります。
こういった儀式を済ませておけば、設置した新しい仏壇に魂入れをして、すぐに位牌を安置できるでしょう。
位牌を持ち運ぶ際には、仏壇がない場合と同様に、風呂敷などに一旦包んでから移動をします。

移動した位牌は、正しい置き方・並べ方を守ることが必要不可欠です。
ここでは、移動した位牌の正しい置き方・並べ方について詳しく解説します。
仏壇がある場合には、位牌は仏壇の中に安置します。
仏壇を特に用意していないときには、他の場所にスペースを設けて位牌を置くことも可能です。このような場合は、安置についても特に厳しいルールなどはありません。
故人に失礼にならなければ、タンスや机の上、棚の上などに白い布などを敷いて供養のスペースを作り、位牌を安置する方法もあります。厨子などがあると、仏壇がなくても位牌のおさまりがよくなるでしょう。
位牌を並べるときには、正しい方法があるのかどうかも気になるところではないでしょうか。
仏壇がある場合とない場合とでは、少しルールが違いますので、ここではそれぞれのケースにそった並べ方を説明していきます。
例えば仏壇の中に位牌を置く場合は、中段の位置から並べていきます。
目上の人が右にくるように置くのが、位牌を安置するときの作法です。また、上段から目上の人を並べていくのも、ルールの1つです。
例えば、立場が上にあたる曾祖父や曾祖母は上の段に、祖父や祖母は下の段にそれぞれ安置をします。仏壇の大きさや位牌のサイズなどを考えながら、バランスのよい配置法を考えましょう。
仏壇がないときは、中央に置いた位牌の手前に香炉を置き、右側にろうそく立て、左側に花立てを置きます。
リンは打ちやすい位置を考え右側の手前に置きます。
位牌が必要ないと考えている人は、位牌なしで供養する方法を知っておくと安心です。
ここでは、位牌なしで供養する方法について詳しく解説します。
位牌を購入しない人は、永代供養を行うと良いでしょう。
永代供養とは、寺院や霊園が管理する場所に故人さまのご遺骨を納めて供養する方法です。自宅に仏壇を置く必要がないため、位牌も不要となるケースが多いです。
位牌が必要な場合は自宅で保管しても問題ありませんが、お寺に預けたり、お炊き上げしてもらったりすることで、お手入れなどの負担を軽減できます。
永代供養を行うためには数十万円〜数百万円の費用がかかりますが、処分するのは気が引けるものの、かといって自宅に置いておけない場合は永代供養が安心です。
位牌を自宅に祀りたい場合は、手元供養という方法もあります。
手元供養とは、故人さまのご遺骨を自宅に祀り、供養する方法です。
位牌だけ手元に置いておくことが可能なため、常に故人さまを身近に感じていたいというお気持ちのある人は、ぜひ手元供養をお選びください。
手元供養であれば、永代供養よりも費用を抑えられます。
場所的にも予算的にも仏壇を置く余裕がないものの、位牌だけは置いておきたいということであれば、手元供養を選択肢に入れましょう。
位牌なしで供養する場合は、過去帳や法名軸など代わりのものを祀ってもOKです。
過去帳も法名軸も位牌の代わりに仏壇に飾るもので、過去帳には故人さまの情報、法名軸には故人さまの法名や没年が書かれています。
故人さまの位牌がなくても、過去帳や芳名軸があれば代わりとすることが可能なため、事情があって位牌なしで供養したい場合に良いのではないでしょうか。
無宗教の場合、位牌は原則不要となります。
位牌は、仏教などで故人さまの魂が宿る場所とされ、供養を行うのに必要不可欠なものとされていますが、それはあくまでも仏教の人の考え方です。
神道やキリスト教では、また別の考え方をすることもありますが、根本的に無宗教の人は位牌も不要と考えて問題ありません。
また、仏教であっても浄土真宗の人は位牌を置く必要がありません。
浄土真宗では、故人さまがお亡くなりになるとすぐに成仏すると考えるため、魂を宿らせる場所としての位牌は不要とされます。
なお、以下の記事では位牌の必要性についてより細かく解説しているため、気になる人はあわせて参考にしていただけると幸いです。
こちらの記事を読んでいる方におすすめ こちらの記事を読んでいる方におすすめ

位牌の魂入れや魂抜きは、故人さまのために必要な儀式となります。
新たに位牌を購入した場合は魂入れ、位牌を別の場所に移動させたり処分したりする場合は魂抜きが必要となりますが、いずれも故人さまを供養するために必要な儀式です。
故人さまがお亡くなりになった場合、仏壇を設置すると決めた場合は位牌の魂入れや魂抜きについて知っておくと安心です。
なお、身内が初めてお亡くなりになって何をすれば良いかわからない場合は、よりそうお坊さん便をはじめとするプロに相談しましょう。
よりそうお葬式は位牌も販売しているため、必要に応じてよりそう仏壇選びの公式ホームページもご確認ください。
「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。
※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。



位牌
位牌とは|仏壇があれば位牌は必要ない?
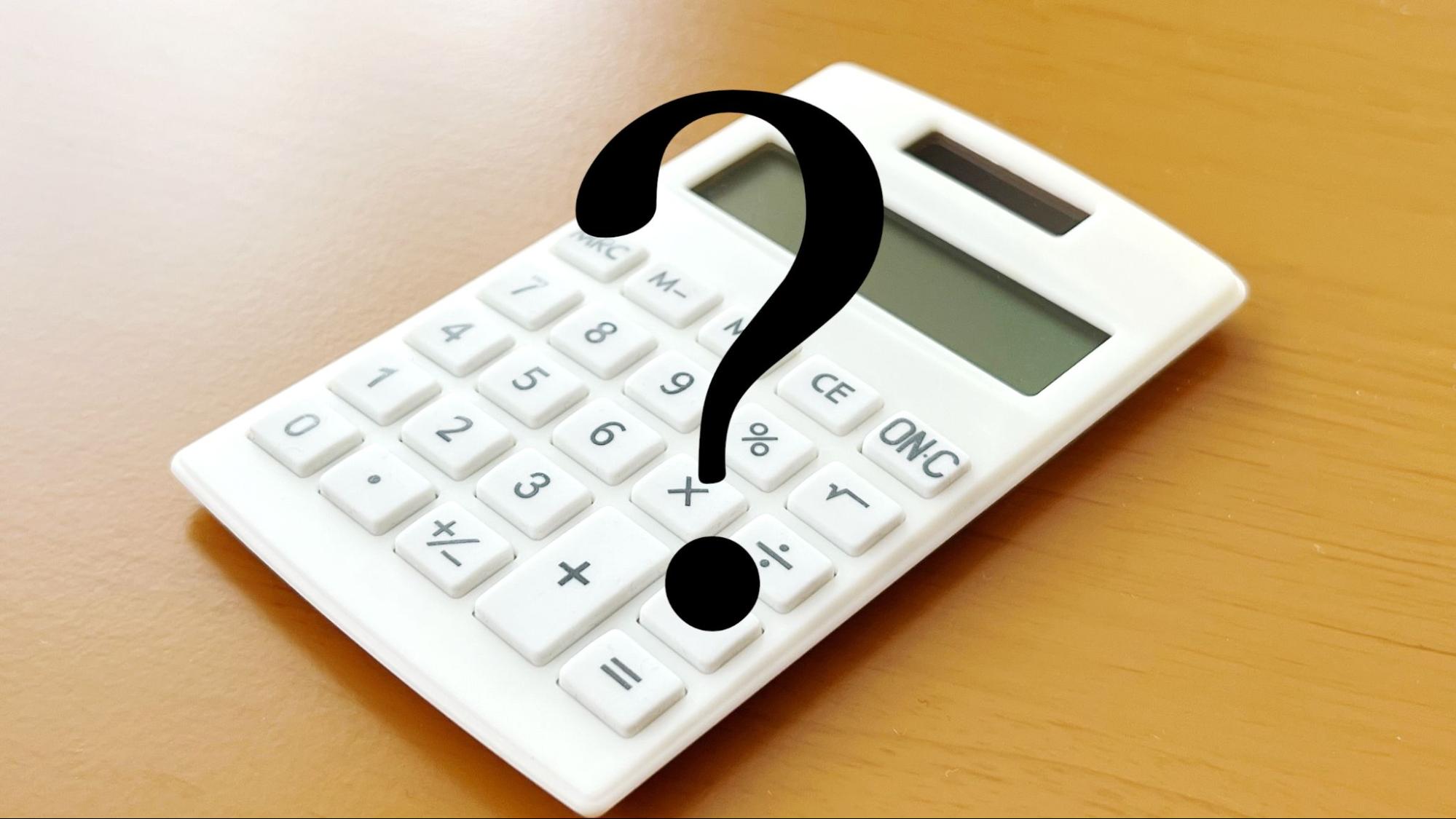
位牌
正しい位牌の購入とは?|実際に位牌を購入する手順

位牌
本位牌の素材|3つの種類と素材の違い

位牌
位牌の価格相場|位牌の種類ごとの価格目安

位牌
浄土真宗に位牌は必要ない?|浄土真宗の位牌の考え方

位牌の魂入れ・魂抜きは必要ない?タイミングや注意点を解説

位牌堂とは何か?位牌を安置して供養するとは何か

本位牌の素材|3つの種類と素材の違い

位牌をまとめて供養する際に抑えておきたい大事なこと

位牌の文字入れと書かれた戒名・俗名の意味とは

位牌とは|仏壇があれば位牌は必要ない?
横にスクロールできます

位牌とは|仏壇があれば位牌は必要ない?

位牌の文字入れと書かれた戒名・俗名の意味とは

位牌の魂入れ・魂抜きは必要ない?タイミングや注意点を解説

本位牌の素材|3つの種類と素材の違い

夫婦位牌って知っていますか?位牌の選び方や気をつけること

位牌をまとめて供養する際に抑えておきたい大事なこと
横にスクロールできます