
-
終活
-
老衰の死亡までの期間は?ご家族が準備することや心構えについて解説

生前葬とは、故人さまがお亡くなりになる前に行うお葬式のことです。
お世話になった人に感謝の気持ちを伝えたり、お別れを直接告げたりするために生前葬を選ぶ人がいて、新しいお葬式の形として受け入れられています。
この記事では、生前葬の基本概要や生前葬をする理由、形式や流れ、参列する際のマナー、場所や費用、よくある質問について詳しく解説します。
生前葬について知りたい人は、ぜひ最後までご覧ください。

生前葬とは、故人さまが生きているうちに自分自身で執り行うお葬式のことです。
本人が元気なうちに執り行うことで、お世話になった人に感謝の気持ちを伝えたり、お別れを直接告げたりできる点が魅力となります。
本人の意向通りにお葬式ができるため、より納得しながら執り行えるのはもちろん、喪主やご遺族の負担を軽減することができます。
人生を振り返り、節目となる年齢を祝いたい場合や定年退職を機に社会活動に区切りをつけたい場合、病気などで余命が限られている場合などが、生前葬を行うのに適しています。
どのようなお葬式が向いているかは本人によって変わりますが、生前葬なら要望通りに執り行うことが可能です。
以下の記事では葬儀の種類について詳しく解説しているため、合わせてご覧ください。
こちらの記事を読んでいる方におすすめ


生前葬をする理由は十人十色です。ここでは、生前葬をする主な理由について詳しく解説します。
生前葬は、お世話になった人に感謝の気持ちを伝えるために執り行われます。
故人さまがお亡くなりになった後だとお世話になった人に感謝の気持ちを伝えられませんが、生きている間であれば本人にありのままの気持ちを届けることが可能です。
親しいご友人をはじめ、学校や職場で良くしてくれた人などに感謝を伝えることで、気持ちの整理ができるのではないでしょうか。
生前葬は、お葬式の負担を軽減するために執り行われます。
故人さまがお亡くなりになってからお葬式を執り行う場合、喪主やご遺族が葬儀社と相談して決めていく必要がありますが、すべての手続きを行うのは大変です。
故人さまを失った悲しみのなか、求められる手配を全部済ませるだけでも一苦労でしょう。
しかし、本人がご存命であれば、自分自身で葬儀社に依頼してお葬式を執り行えます。いつ行うか、誰を呼ぶか、どこで行うかなども自分自身の裁量で決めることが可能です。
結果的に、後々の喪主やご遺族の負担軽減につながるでしょう。
生前葬は、終活の一環として執り行う人も一定数いらっしゃいます。
人生を振り返って節目となる年齢を祝いたい場合や、定年退職を機に社会活動に区切りをつけたい場合、病気などで余命が限られている場合などに執り行います。
自分自身が求めるスタイルでお葬式が執り行えるため、細部まですべて決めたいという人に適しています。
生前葬を執り行うことで、本人はもちろんご家族や親族も一緒に感情の整理ができるため、最近では身内と話し合いながら生前葬を執り行う人も珍しくありません。
生前葬は、お別れを直接告げるために執り行われることもあります。
故人さまがお亡くなりになった後だとお別れを直接告げられませんが、生きている間であれば本人に最後の言葉を直接届けることが可能です。
両親や祖父母、兄弟姉妹や配偶者、子や孫などにお別れを告げることで、今後について話し合う場にもなるでしょう。

生前葬の形式や流れは普通のお葬式と同じ形で執り行われますが、本人がご存命ということも相まってパーティー形式で執り行われることもあります。
ここでは、生前葬の形式や流れについて詳しく解説します。
生前葬の形式は、一般葬や家族葬のように執り行われることがありますが、基本的には本人の希望通りに行われるのが一般的です。
通常のお葬式ではお通夜・葬儀・告別式・ご火葬という形式で執り行いますが、生前葬はその限りではありません。
パーティー形式など、比較的自由に執り行われます。
生前葬の内容としては、思い出の曲の生演奏をはじめ画像や動画の上映会、カラオケ大会、ビンゴ大会など、お葬式と比べて明るく華やかに執り行われます。
花束や記念品の贈呈、本人によるスピーチ、趣味の披露など、生前葬を執り行う本人が主催したイベントを盛り込めるのが生前葬の魅力といえます。
もちろん、本人が望めば一般葬や家族葬と同様の形で執り行うことが可能なため、まずは葬儀社と話し合ってみるのが良いでしょう。
生前葬はイベントを企画している業者にも依頼できるため、形式に応じて選んでください。
生前葬は、招待客や内容を自由に決められるのはもちろん流れも自由です。
カジュアルなスタイルで執り行う場合もあれば、フォーマルなスタイルで執り行う場合もあるため、本人が求めているものによって流れが変わります。
代表的な生前葬の流れとしては、以下のようなものがあります。
どの生前葬もまずは開式の挨拶を行い、本人から挨拶が行われるのが一般的です。本人が病気などで身動きが取れない場合は、関係者が挨拶を行います。
その後はエピソードを交えた会食を行ったり、メモリアルムービーの上映を行ったりと本人が求める形で生前葬を進めていくのが基本的な流れです。
すべてのセレモニーが終わったら閉式の挨拶を行い、解散となります。なお、生前葬ではお坊さんは呼ばず、身内だけで済ませることもあります。
どうしても一般葬や家族葬と似た形式で行いたい場合はお坊さんを呼ぶこともありますが、必ず呼ぶ必要があるわけではないため、本人の判断で問題ありません。

生前葬に参列する際は、マナーを知っておくと安心です。ここでは、生前葬に参列する際のマナーについて詳しく解説します。
生前葬では、挨拶は和やかな気持ちで済ませるのがマナーです。
一般葬や家族葬の場合は、葬儀場に設置されている受付でお悔やみの言葉をお伝えし、香典などをお渡しするのがマナーとなります。
しかし、生前葬は本人が元気なうちに執り行うため、和やかな雰囲気で問題ありません。
生前葬であっても、忌み言葉や重ね言葉など縁起の悪い言葉は避けるのがマナーとなります。
死を連想させる「4」、無を連想させる「6」、苦を連想させる「9」などの不吉な数字には配慮が必要です。
生前葬では、演出に対して笑顔や拍手してもいいとされています。
通常のお葬式では笑顔や拍手はご法度とされていますが、生前葬は明るく華やかに執り行われるため、基本的には演出も派手です。
何らかの演出があった場合は、温かい気持ちで笑顔や拍手を送るようにしてください。
生前葬は会費制で執り行われる場合があるため、招待状に会費が記載されていたら、白い封筒に入れて持参してください。
会費は生前葬の総費用を予定参列者数で割って計算されているため、他に現金を持参する必要はありません。
何も会費の指定がない場合は、主催者やお手伝いされている人に問い合わせましょう。
生前葬では、お香典は持参しなくてもいいとされています。
普通のお葬式ではお香典を持参するべきですが、生前葬は会費を持参することに加えて本人もご存命であるため、お供え物も含めて原則は不要です。
香典の代わりに、本人を温かく見守るようにしましょう。
生前葬はラフな雰囲気で執り行われますが、身だしなみは整えるのがマナーです。
髪型がボサボサだったり服装がボロボロだったりすると、本人はもちろん他の参列者にも不快感を与えるため、きれいな身だしなみを心がけてください。
招待状で平服の指定があれば、平服で参列しましょう。
ドレスコードが指定されている場合もされていない場合も、男性はスーツやジャケット、女性はアンサンブルやワンピースで参列するのがマナーとなります。
ただし、私服での参列がOKとされている場合もあるなど、状況によって変わります。判断しかねる場合は、主催者やお手伝いしている人に聞いておくと安心です。

生前葬の会費や場所は千差万別です。ここでは、一般的な生前葬の会費や場所について詳しく解説します。
生前葬の会費は規模によって変わるため、注意が必要です。
大規模な生前葬の場合は会費が高くなる傾向にありますが、当然ながら小規模な生前葬の場合は会費が低くなります。
生前葬に参列する場合、どれくらいの会費が必要なのかは招待状に記載されているため、まずは招待状を確認し、何も記載がなければ本人に確認しておくと安心でしょう。
生前葬の場所は、宴会場などで執り行われるのが一般的です。
生前葬は本人の意向を重視するため、あまりかしこまったものにしたくない人のなかには、カジュアルなホテルやレストランで執り行うことがあります。
逆に葬儀場で一般葬や家族葬と同様に執り行うこともあるなど、場所は状況によって変わってくるといえるでしょう。
生前葬は、故人さまがお亡くなりになる前に執り行うお葬式のことです。
通常は本人がお亡くなりになったタイミングで一般葬や家族葬、火葬式(直葬)を執り行いますが、生前葬は本人が生きている間に執り行います。
本人が元気なうちに行うことで、お世話になった人に感謝の気持ちを伝えたり、お別れを直接告げたりできるのが魅力です。
一方、生前葬についてはご家族やご親族から反対されることもあるため、身内で話し合っておくことが重要となります。
お亡くなりになってからお葬式を行うのかも、話し合っておく必要があります。
お葬式を執り行うことになった場合は、よりそうお葬式にお問い合わせください。
よりそうお葬式では、家族葬や火葬式(直葬)をはじめ、一般葬など複数のプランに対応しているため、ご予算に合わせてお選びいただくことが可能です。まずは当社の公式ホームページより、各種プランをご検討の上、一度ご相談いただけると幸いです。
「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。
※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

終活
老衰の死亡までの期間は?ご家族が準備することや心構えについて解説

終活
終活のやることリスト!大事な10項目と解説

終活
終活はいつから始めればいいのか?誰でもすぐに始められる終活の解説

終活
終活とは?終活の方法やタイミング、終活の内容を解説

終活
終活を40代から始めるのは早くない!終活の具体的な内容とその効果を解説

遺影写真、選び方や加工する時に気をつけたいこと

生前整理とは?始める時期や進め方

縄文時代の葬儀や埋葬方法・弥生時代の葬儀や墓制について

献体とは?登録条件や献体した場合の葬儀の内容を解説

お墓はいらない人が考える0葬、墓じまいという考え方

病院には必ずある?霊安室の意味や場所について知りたい
横にスクロールできます
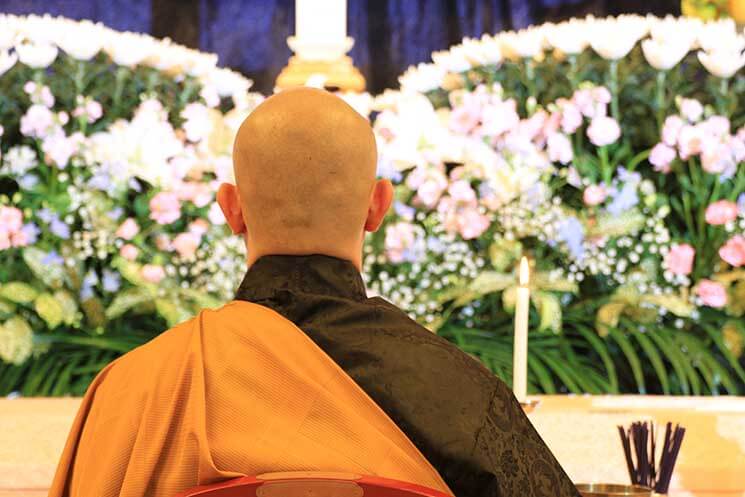
自分の菩提寺がどこかご存知ですか?葬儀や法要を依頼する方法と流れ
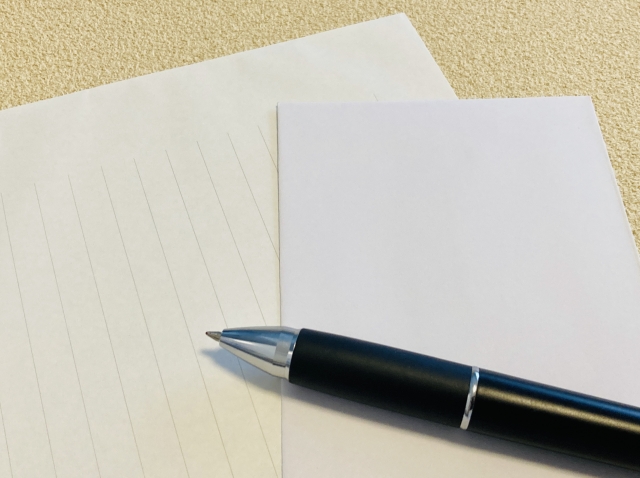
エンディングノートの書き方は?内容やメリット、注意点を解説

献体とは?登録条件や献体した場合の葬儀の内容を解説

看取りの意味・定義・準備・注意点などについて

老衰死で穏やかな最期を迎えるために考えたいこと。老衰死の前兆とは?

生前葬とは?形式や流れ、参列する際のマナーを解説
横にスクロールできます