
-
葬儀のマナー
-
意外に知らないお通夜の持ち物!マナーはあるの?

冠婚葬祭のマナーはとても重要です。特に親族の葬儀となると、香典を頂いた方々へのお返しなどを考える必要があります。具体的にいうと、葬儀の準備や葬儀自体が終わり、少し落ち着いた時期に、今度は満中陰志を考えなければなりません。
しかし、満中陰志という言葉自体を聞いたことがないという人も多いでしょう。この満中陰志という言葉は、一定の地域で使用されている言葉であり、それ以外の地域では主に志という言葉が使用されているのが通常です。
今回は、この満中陰志という言葉の意味と、その選定方法やマナーについて解説をおこなっていきます。
満中陰志とは四十九日法要における香典返しのことを言います。先述したように、この満中陰志という言葉は、一定の地域で使用されており、その他の地域では主に志という言葉を使用するのが一般的です。
具体的には、主に関西地域で満中陰志という言葉が使用されており、九州や東日本では志という言葉を使用するのが一般的です。
この満中陰志という言葉の意味ですが、仏教では人が亡くなって49日の間を「中陰」といい、49日目の日を中陰が満ちる日として「満中陰」とよんでいるため、満中陰に送る志として満中陰志という言葉が使用されています。
そして、この満中陰を迎えることが、忌明けを意味することになり、この忌明けから1か月程度を目安に、香典を頂いた方々への返礼として香典返しを配っていくことが基本的な葬儀のマナーです。
満中陰志は「無事に葬儀を終え、忌明けを迎えることができました」という報告を兼ねて行うものです。そのため、満中陰志を送る時期は基本的には忌明けを迎えた四十九日法要を終えた後というのが一般的といわれています。
しかし、近年では四十九日法要の前、つまり葬儀当日に満中陰志を渡すことも増えています。これは遠方からの参列者一人ひとりに送付する手間を省くためであったり、金銭的な負担をできるだけ避けるためです。
また、宗教によっても満中陰志を渡す時期は若干異なりますので注意が必要になります。
キリスト教の場合、日本の慣習に準じてだいたい1か月後を目安に追悼儀礼(プロテスタント「記念式」、カトリック「追悼ミサ」を行うケースが多いようです。満中陰は仏教用語なので使用しませんが、日本式に合わせて満中陰志を送る際は、表書きに「志」と書きます。
神式の場合には、五十日祭というのが仏教四十九日法要に相当しますば、満中陰は仏教用語なので使用せず、「偲び草」「茶の子」「志」といった表書きを使用します。

満中陰志を送る際にもっとも重要なことが、いったい何を満中陰志の品物として選択するのかということと、満中陰志にかける金額です。
基本的に満中陰志を送る際は、品物とお礼状を添えて、のしをつけて送ります。
品物に関してですが、満中陰志で送る品物は形がなくなるものを送るのが一般的です。
具体的には、お茶やお菓子、石鹸などが好まれています。また、最近では満中陰志としてカタログギフトを送る場合もあります。
注意点としては生ものや祝い酒は満中陰志には不向きです。
そして、金額の目安ですが、頂いた香典の半返しというのが基本といわれています。しかし、葬儀当日に満中陰志を渡す場合には、主に2千円から3千円相当の満中陰志を準備すると良いでしょう。
その理由については、故人が肉親以外の場合、香典の相場がだいたい5千円ほどといわれているからです。
しかし、当日に1万円以上の高額な香典をいただく場合もあります。その時は四十九日法要が終わり次第、不足分の金額に相当する満中陰志を送ることが一般的です。
こちらの記事を読んでいる方におすすめ

満中陰志は香典返しの意味ですが、満中陰志を受け取った人も、満中陰志が届いたらそのお礼を遺族に伝える必要があるのでしょうか。その答えは「お礼は必要ない」です。
そもそも満中陰志とは香典返しとして送られます。つまり、頂いた香典に対してのお礼として送られるのが満中陰志ですので、基本的にお礼にお礼で返すのは逆にマナー違反です。
もし、なにか一言、満中陰志が届いた際に言葉をかけたい場合には、手紙などにお見舞いの言葉を添えて送付しましょう。
しかし、近年は手紙を送るという行為自体が少なくなり、代わりに電話やメール、ラインといった手軽なツールを利用する人も増えています。ただし、満中陰志が届いた際の連絡ではこの部分には注意が必要です。
メールやラインといったツールについては、親しい間柄であったり、日頃から連絡手段としてよく使う相手であれば問題ないでしょう。 電話で連絡する際は、事務的なお礼よりも話を聞いてあげる気持ちで寄り添います。
ここまで、満中陰志に関して解説をおこなっていきました。満中陰志は送る側、もらう側、それぞれがお互いのことを考える必要があります。
特に、満中陰志を送る側、つまり遺族は葬儀の準備やその後の手続きなどで余裕がないかもしれません。
しかし、故人の名誉のためにも、この満中陰志のマナーについてはしっかりと把握しておくことが重要です。また、満中陰志を送られた方も、残された遺族の気持ちを一番に考えて、満中陰志が届いた際の対応を考えておく必要があります。
葬儀のマナーはとても重要です。遺族は大変ですが、慌てずに適切な満中陰志を準備できるようにしましょう。
「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。
※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

葬儀のマナー
意外に知らないお通夜の持ち物!マナーはあるの?

葬儀のマナー
お通夜に持参する香典のマナー!

葬儀のマナー
お通夜とは?意味やマナーを徹底解説!

葬儀のマナー
お通夜と告別式の違いは?どちらに参列すべき?知っておきたいポイントや参列マナーを紹介

葬儀のマナー
お通夜での挨拶マナー!立場別に紹介

【訃報の連絡で使える文例付き】訃報のお知らせの意味と書き方

通夜・葬儀、喪服でのハンカチは何色?男女の違いは?お葬式の持ち物マナー

身内の不幸の職場への連絡はメールで大丈夫?忌引きメールのマナーを解説

香典をいただいた時の言葉やマナーとは?お礼の伝え方やメールを送る場合の書き方を解説

淋し見舞いとは?書き方と渡し方

友達の親が亡くなった時にかける言葉は?参列の判断基準や対応方法を紹介
横にスクロールできます
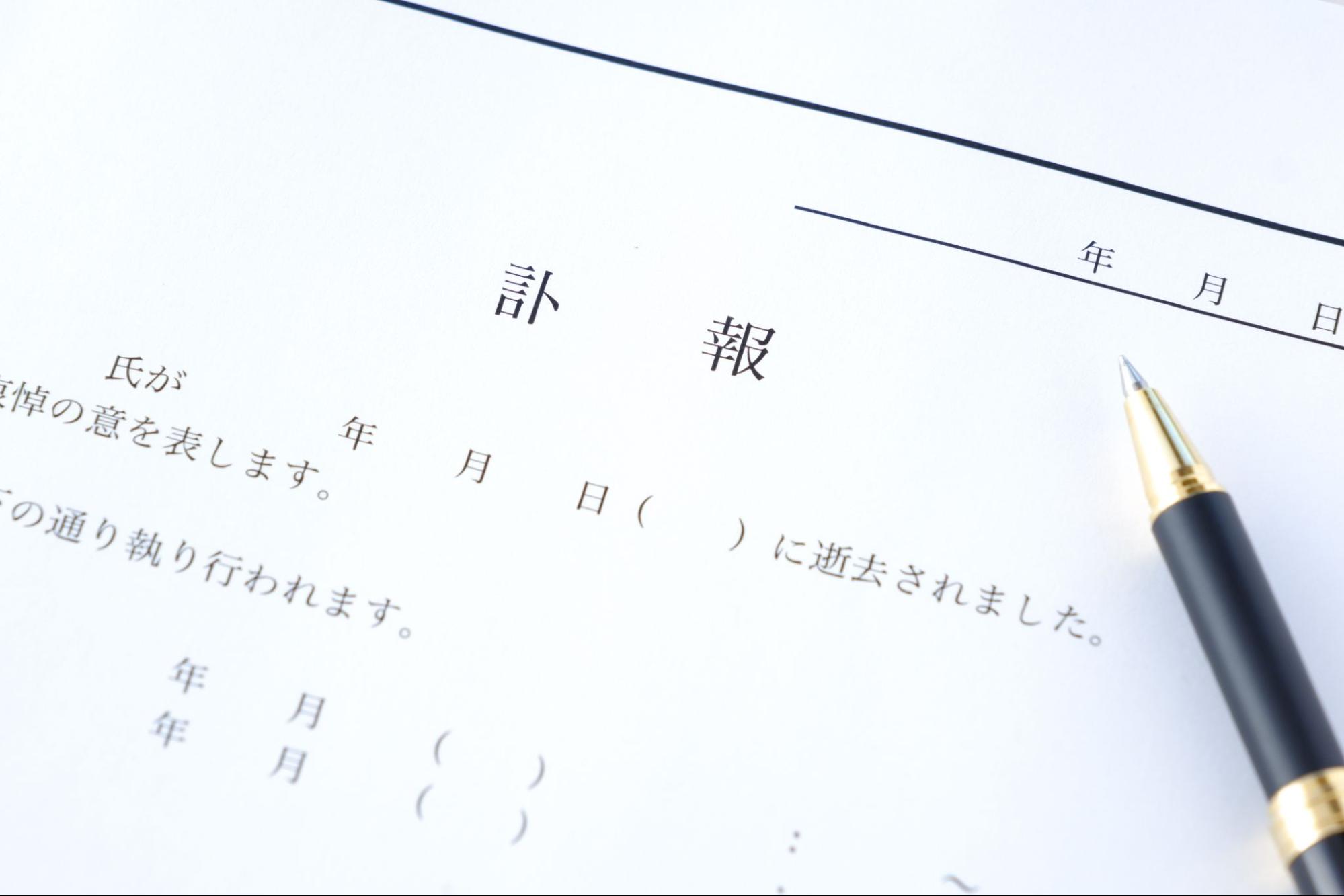
お葬式の連絡はいつする?相手・注意点・方法・例文を解説

一周忌に用意するものは?喪主側と参列者側でそれぞれ解説

香典返しはいくらが目安?適切な金額をケース別に紹介

意外と知らない?弔電の宛名や宛先に関するマナーまとめ

お通夜とは?意味やマナーを徹底解説!

お通夜と告別式の違いは?どちらに参列すべき?知っておきたいポイントや参列マナーを紹介
横にスクロールできます