
-
終活
-
老衰の死亡までの期間は?ご家族が準備することや心構えについて解説


「あと半年の命です」、「よくもって3ヶ月です」。大切な家族がそんな余命宣告をされてしまったら、あなたはどうしますか?
それまで普段通りの生活をしていた人が、体に痛みや不調を感じて受診したところ、末期がんや心臓病などの病気が見つかり、治療をしても治る見込みがないと医師が判断したとき告げられるのが、“余命宣告”です。
余命期間がどれくらいだったとしても、ご家族は、絶望の淵に立たされ、しばらくは何も考えることができなくなるかもしれません。しかし、そのままいつまでも絶望しているわけにはいきません。
われわれ「よりそうお葬式」では年間3万件以上のご相談をお受けしていますが、入院やがん告知、余命宣告など健康状態の悪化をきっかけとしてお電話される場合が多くなっています。ご家族に“その時”がやってきて、二度と会うことができなくなった後、少しでも悔やむことが少なくて済むよう、「家族が余命宣告を受けたらやっておきたいこと」を知っておいてください。
医師から「末期の肺がんで長くて半年の命です」と告げられたとしても、「ああそうですか」とすんなり納得できる人は、まずいないでしょう。
一度は「まさか?!」と疑いたくなるのが人情です。また、余命半年と宣告されてから何年も生きたという人の話を聞くことも少なくありません。
余命宣告されても、「本当はもっと生きられるのではないか?」、「何か別の治療法があるのではないか?」と考えるのも当然です。
本人と家族が納得するためにも、まず考えたいのは、別の医師に診断してもらうセカンドオピニオンを受けることです。
担当医に失礼なのではないか?と心配になるかもしれませんが、他の医師に別の視点から診断してもらうセカンドオピニオンを受けることは、今や当たり前です。
セカンドオピニオンを受けるときは、最初に診断した医師から検査結果やデータをもらって、次の医師に提出しましょう。申し訳ないからとこっそり別の病院を受診すると、同じ検査を再び受けることになり、体にとっても負担です。
セカンドオピニオンを受けても診断結果に変わりはなく、余命宣告を受け入れざるを得なくなったとき、患者や家族が抱くのが絶望感です。
家族も現実を受け入れられず、悲しんだり「なぜ自分の家族が?」と怒りを覚えたりするかもしれません。
しかし、考えてみてください。家族以上に辛くやりきれない気持ちを抱えているのは、患者本人です。不安から苛立ち、落ち込み、自暴自棄になることもあるでしょう。
そんな患者を支えることができるのが、家族です。
ときには励まし、ときには静かに見守りながら、家族がいつもそばにいることを言葉と態度で示し続けてください。
絶望は病状の進行を早めます。余命宣告を受けても、絶望しない、絶望させないことはとても大切です。
誰にでも「一度やってみたい」と思っていることが、1つや2つはあるものです。「行ってみたい場所」や「食べたいもの」、「会いたい人」だっているでしょう。
余命宣告というのは、命の期限が区切られることですから、「いつか」などと悠長なことを言ってはいられません。
全ては難しいかもしれませんが、本人が望むことはできるかぎりやらせてあげるようにしましょう。
いつかは来る“その時”に、残された家族が直面するのは、「誰に連絡すればいいのか?」、「お金はどこにあるのか?」、「持ち物の処分はどうすればいいのか?」という3つの問題です。
家族でも知らない交友関係を持つ人は少なくありませんし、葬儀費用を積み立てしていたり、タンス貯金があったりする場合もあります。
家族の死後、趣味のコレクションをごみとして処分したら、後でとんでもないプレミア価格が付いていたことがわかったという話もあります。
死期の迫った家族を相手にそんな話はできないと思われるかもしれませんが、本人だって気がかりでしょう。家族だからこそ話し合える、話し合わなければいけない問題だと認識しましょう。
「臓器提供」は、死後に眼球や内臓などの臓器を、それを必要とする人に提供することで、「献体」は医学の発展のため死後の体を解剖などに役立ててもらうことです。
どちらも、本人が希望していても家族の承諾が得られなければ行われません。
もしも、本人が自分の死を他の人のために役立てたいと考えているとしたら、それを手助けするのも家族の役目です。可能なかぎり希望を聞いておきましょう。
病状が進行し、本人が意思表示できないような状態になったとしても、病院は延命治療を行います。さまざまな装置を使い、薬を投与し、場合によっては意識がないまま長く生かされてしまうこともあります。
しかし、そうした最期ではなく、いわゆる 「尊厳死」を望む人もいます。尊厳死とは、過剰な医療行為を避け、尊厳を持って迎える自然な人の死のことです。
本人は延命を望んでいなかったとしても、家族がそれを知らなければ、医師から問われた際、延命装置を外す決断をすることは難しいでしょう。どんな最期を迎えたいのか?は必ず聞いておくべきでしょう。
「まだ早い」とお考えかもしれませんが、先に葬儀について考えておくことは余命宣告を受けた方のためでもあります。
日本消費者協会が2022年に発表した「第12回『葬儀についてのアンケート調査』」によると、2017〜2019年の葬儀一式費用の全国平均相場は121.4万円とされています。
費用が高くなる原因の多くが事前の準備不足にあります。「今はまだ葬儀のことは考えたくない」と後回しにしていたところ、病状が急変して、予定より早く“その時”が来てしまい、バタバタとした状況の中で葬儀社が進めるままにオプションを付けてしまい費用が高額になってしまった例もあります。
いざという時慌てないためにも、ぜひ資料請求をして目を通してみてください。
「よりそうお葬式」はフリーダイヤルを設置して、24時間365日無料で相談を行っております。葬儀に関して不安なことがございましたらお気軽にご連絡ください。
以上、ご紹介した7つの項目を参考に、大切な家族が旅立った後、「精一杯やってあげることができた」、「最高のお葬式で送ることができた」と納得できるようお過ごしください。
「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。
※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

終活
老衰の死亡までの期間は?ご家族が準備することや心構えについて解説

終活
終活のやることリスト!大事な10項目と解説

終活
終活はいつから始めればいいのか?誰でもすぐに始められる終活の解説

終活
終活とは?終活の方法やタイミング、終活の内容を解説

終活
終活を40代から始めるのは早くない!終活の具体的な内容とその効果を解説

遺影写真、選び方や加工する時に気をつけたいこと

生前整理とは?始める時期や進め方

縄文時代の葬儀や埋葬方法・弥生時代の葬儀や墓制について

献体とは?登録条件や献体した場合の葬儀の内容を解説

お墓はいらない人が考える0葬、墓じまいという考え方

病院には必ずある?霊安室の意味や場所について知りたい
横にスクロールできます

親族が急逝・亡くなったときどうしたらいい?必要な手続きとやるべきこと
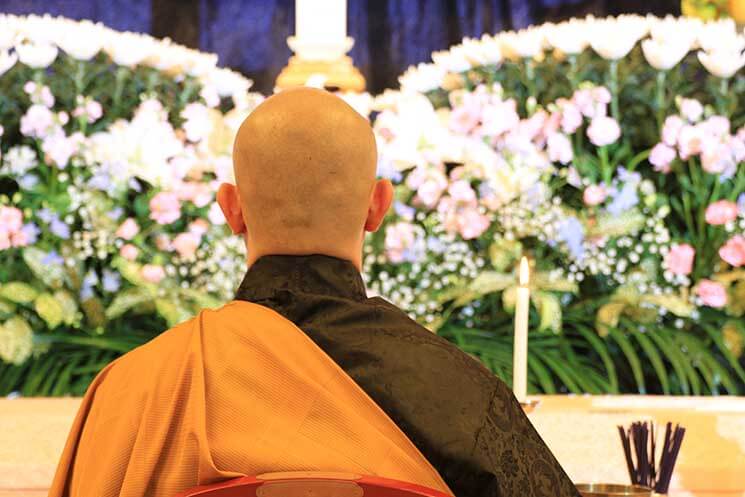
自分の菩提寺がどこかご存知ですか?葬儀や法要を依頼する方法と流れ
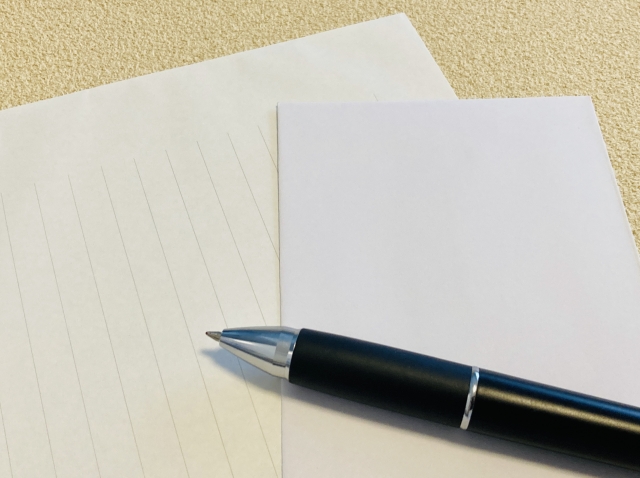
エンディングノートの書き方は?内容やメリット、注意点を解説

献体とは?登録条件や献体した場合の葬儀の内容を解説

看取りの意味・定義・準備・注意点などについて

老衰死で穏やかな最期を迎えるために考えたいこと。老衰死の前兆とは?
横にスクロールできます