
-
終活
-
老衰の死亡までの期間は?ご家族が準備することや心構えについて解説

葬式は従来、当たり前のように遺族が故人の親類縁者や近所の方々に協力してもらいながら、自宅や菩提寺で執り行っていました。
しかし、近年では親類縁者・ご近所の方々との付き合いが変化したことに加え、一般の参列者が葬儀・告別式に参列しやすいように、「斎場」で行われることが多くなりました。
今回は、この斎場について説明します。この記事を読めば、斎場の種類や費用の目安、そのサービス等の基本的な知識を得られることでしょう。
斎場は、通夜・告別式が行うことができる場所を指します。
従来からよく行われていた自宅葬から会場葬へ、執り行う場が変化するに従い葬儀会場として使用される場所が「斎場」と呼ばれるようになりました。
主に斎場で通夜・告別式が行われるようになった理由は次の通りです。
斎場は通夜・告別式、施設によっては火葬も一緒にできる便利な施設といえます。
概ね、式に関しては葬儀業者に依頼をするケースが多くなり、斎場・僧侶の手配や、式に必要な準備もそのほとんどを任せることができます。
これは、遺族が親類縁者やご近所の協力を得られなくても、葬儀業者に頼んでいれば斎場で式が滞りなく行えることを意味します。
つまり、親類縁者・ご近所との関係が希薄化した現在では、非常に都合のよいシステムといえます。
都会や地方都市では、自宅が一戸建てよりマンションが多くなってきています。通夜のために故人を自宅に安置しようにも、同じマンションに居住する方々にとっては、ご遺体を搬送することに抵抗を感じる場合があります。
そのため、自宅ではなく斎場へご遺体を安置することは、周囲の居住者の感情に配慮した対応といえます。
斎場は、最初から通夜・告別式が行うことができる場所として呼称されていたのかと言えば、そうではありません。
もともと斎場とは、祭祀を行う際の清浄な場所を意味します。恒常的に設置された神社や、その仮設建物が該当します。
神道で使用された仮設建物は、神官・遺族が神式の葬儀を行う際に建てられました。
神道では、原則として社殿や境内に遺体・遺骨をもちこむことが許されていないため、葬儀を行う前にその都度、神社から離れた場所に建物をつくり葬儀をしました。
斎場には、大きく分けて公営斎場と民営斎場があります。
どちらも故人を悼み・供養を願う通夜・告別式を行う場としては、申し分のない設備となっています。
しかし、それぞれにメリット・デメリットは存在します。
公営斎場とは、市町村や一部事務組合(※)、公社が運営する斎場のことです。
斎場の名称としては、例えば「○○○市営斎場」というように、市町村名の後にそのまま斎場を付けている場合が多いです。
メリットは次の通りです。
デメリットは次の通りです。
※一部事務組合・・・複数の地方自治体や特別区が、行政サービスの一部を共同で実施することを目的として設置された組織です。斎場(火葬場)の運営のみならず、消防施設や廃棄物処理場の運営等も該当します。
民営斎場とは、企業、宗教団体等が運営する斎場のことです。
民営斎場の名称としては、「○○会館」や「○○ホール」等と、直接「斎場」と付けていない施設が多いです。
メリットは次の通りです。
デメリットは次の通りです。
斎場は、式の際にどのくらいの広さのホールを使用するかにより費用にかなりの差が出ます。
また、都心にあるか地方にあるかによっても、公営斎場を利用するか民営斎場(自社斎場・貸斎場・寺院斎場)を利用するかによっても、大きく異なります。
公営斎場は、5~10万円程度で利用できます。民営斎場の1/3~1/2の費用で利用することができます。
ただし、費用が安いからといって誰でも利用できるわけではありません。利用対象は、原則として個人又は喪主が、斎場を運営する市町村の住民でなければいけません。
対象の住民以外の方も利用できる場合がありますが、地域住民より高い利用費を支払うことや、そもそも地域住民以外の方の利用を認めないことを明示している所もあります。
民営斎場の場合は、①自社斎場、②貸斎場、③寺院斎場に分けて説明します。
葬儀業者により費用に差がありますが、10万円程度となります。
利用料金は20~40万円程度です。ただし、多数の参列者を招いた式の場合は、それなりの広さのホールが必要になるため、費用はその分高額になります。
寺院が所有している斎場の場合は、概ね15~30万円となります。寺院では宗教宗派が問われてしまうため、同じ宗教宗派で無ければ利用できないことが多いです。
また、その寺院の檀家であるかどうかもポイントで、檀家で無い場合には、利用料金が倍になることがあります。
こちらでは斎場のサービスについて紹介します。公営斎場も民営斎場も現在のニーズにあった葬儀ができるように、いろいろなサービスを行っています。
公営も民営も、「家族葬」が可能な斎場が増えています。家族葬とは、親族や近親者のみで執り行う小規模の葬儀を指します。
概ね人数が10人までで葬儀を行え、多くの参列者を呼ばず、時間と費用を抑えることを望む遺族に配慮したサービスとなっています。
宗教にどうしても抵抗のある故人の生前の意向、または遺族の希望で、宗教色を抑えた葬儀が可能な公営・民間の斎場も多いです。
ただし、一律に演出が派手な葬儀や、音楽葬が可能であるわけではないので、どのようなスタイルの葬儀が可能か、事前に運営側に確認を取っておきましょう。
通夜・告別式を行えるので、通夜ぶるまいや初七日法要の宴席を催すことができます。
また、通夜の際に遺族が仮眠をとるスペースがあり、シャワーも常設されている施設が多いです。
火葬場の併設は公営斎場に多いです。通夜・告別式の会場と火葬場が別々なケースのように、参列者を乗車させるためのハイヤー等の手配も必要ありません。スムーズな式の進行が期待できます。
民営斎場に関しては、寺院斎場であるなら運営する寺院へ、葬儀業者の自社斎場または貸斎場を望む場合は、葬儀業者に連絡をして指示に従いましょう。
公営斎場で、火葬場が併設されている施設である時には以下のような手続きの流れとなります。
故人が医療機関で亡くなった際に、医師から記載してもらった死亡診断書と共に死亡届を、故人の本籍地または死亡地、届出人の所在地の市区町村役場へ提出し、死体埋火葬許可証の交付を受けましょう。念のため、事前に提出先の市町村へ準備書類を確認しておきましょう。
[準備書類]
なお、死体埋火葬許可証は、公営・民営のいずれの火葬場であっても必要になります。
公営斎場の運営主体(例えば市町村の場合は、生活環境課等が窓口に該当します。)へ、死体埋火葬許可証を持参し、使用許可申請書を作成します。念のため、事前に提出先の運営主体へ準備書類や施設利用料を確認しておきましょう。
[準備書類]
運営主体の担当者から斎場使用承諾書が交付され、死体埋火葬許可証が返却されます。
斎場使用承諾書および死体埋火葬許可証を斎場係員へ渡します。
なお、公営斎場を利用する際も、葬儀業者に依頼をして葬儀を行う場合には、前述した手続きを代行させることが可能です。葬儀業者に依頼をする際は代行について確認しておきましょう。

こちらでは斎場(葬儀会場)に関する疑問・質問について回答いたします。
くれぐれも式の際には「遅刻は厳禁」です。通夜・告別式の開始約10分前には受け付けを終わらせ、余裕をもって席に着きましょう。
自分の焼香が終わり、全員が焼香するまで時間があるので屋外でタバコを吸ったり、帰宅したりするのは「重大なマナー違反」です。
もしも、用事があって焼香した後に退席する場合は、事前に喪主へその旨を伝えておきましょう。
また、退席の際に他の参列者の迷惑にならないように、あらかじめ後ろの席へ座りましょう。
式が進み出棺の際にも気が緩んではいけません。一般の参列者にとって故人を見送るための最後の儀式です。故人に哀悼の意をあらわすため、霊柩車に棺を収めるときは黙礼して、出発したら合掌または黙祷を行い、故人をお見送りします。
マンション・団地の集会所や居住者用のホールがあれば、そこを葬儀会場にして式場費用を格安に抑えることが期待できます。
ただし、当該施設で葬儀が可能かどうかを事前に確認する必要があります。それに加えて、マンション・団地の管理組合の会長・役員等に協力してもらうことも大切です。
故人や喪主が所属している地域自治会の町内会館を利用できる場合があります。
町内会館を葬儀会場にできれば、こちらの場合も式場費用を格安に抑えることが期待できます。
ただし、この場合も自治会の会長・役員等に協力してもらうことが重要です。
①、②の場合、共に葬儀専用の施設ではありません。そのため、遺体を安置する場所や方法・会場の設営について、葬儀業者と相談してみることをお勧めします。
ただし、ホテルへご遺体をそのまま搬送することはできませんので、焼骨した後にホテルでの葬儀となります。
遺族や参列者の宿泊はもとより、交通の利便性の高さ、洗練された料理やサービス等、遺族・参列者が安心できる葬儀が期待できます。
しかし、葬儀費用は通常の葬儀と比較してかなり高額になります。また、葬儀会場として利用できないホテルもあります。
なお、骨葬ができる場合でも、防火上の理由や、他の宿泊客への配慮から焼香は禁止されています。
斎場も、公営・民営共に現在の利用者のニーズに合ったサービスを提供する施設が非常に多くなりました。
確かに、親類縁者やご近所の助力を借りない葬式が可能になり、喪主や遺族側には便利になりました。
しかし、通夜・告別式を行う目的は、故人を悼み供養を願うことです。どんなに葬儀のスタイルが時代と共に変化しても、故人が天国に行けるようと願う心は、過去も未来も決して変わってはならないはずです。
「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。
※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

終活
老衰の死亡までの期間は?ご家族が準備することや心構えについて解説

終活
終活のやることリスト!大事な10項目と解説

終活
終活はいつから始めればいいのか?誰でもすぐに始められる終活の解説

終活
終活とは?終活の方法やタイミング、終活の内容を解説

終活
終活を40代から始めるのは早くない!終活の具体的な内容とその効果を解説

遺影写真、選び方や加工する時に気をつけたいこと

生前整理とは?始める時期や進め方

縄文時代の葬儀や埋葬方法・弥生時代の葬儀や墓制について

献体とは?登録条件や献体した場合の葬儀の内容を解説

お墓はいらない人が考える0葬、墓じまいという考え方

病院には必ずある?霊安室の意味や場所について知りたい
横にスクロールできます

親族が急逝・亡くなったときどうしたらいい?必要な手続きとやるべきこと
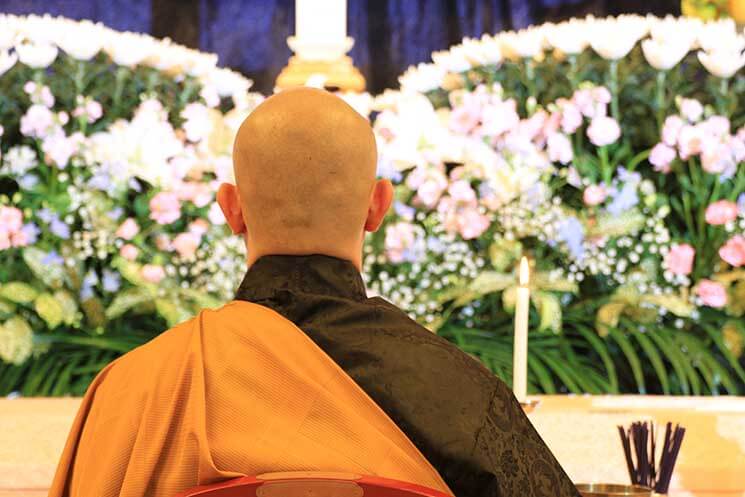
自分の菩提寺がどこかご存知ですか?葬儀や法要を依頼する方法と流れ
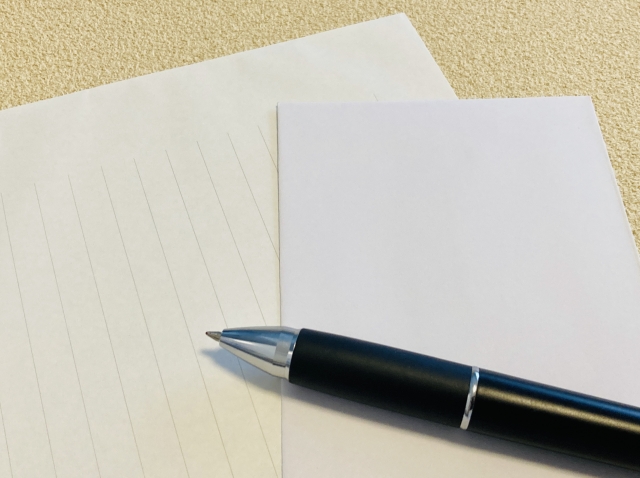
エンディングノートの書き方は?内容やメリット、注意点を解説

献体とは?登録条件や献体した場合の葬儀の内容を解説

看取りの意味・定義・準備・注意点などについて

老衰死で穏やかな最期を迎えるために考えたいこと。老衰死の前兆とは?
横にスクロールできます