
-
葬儀の種類・宗派
-
神式のお葬式で知っておきたい香典袋のマナーは?参列時のマナーや作法を紹介

近年、お葬式のスタイルは多様化しており、「お別れの会」と呼ばれる会が執り行われるケースも増えています。
有名人がご逝去された際に、お別れの場として行われるイメージを持つ方もいらっしゃるかもしれません。実際には一般の方にも選ばれることが多いお別れの形です。
お別れの会は一般的なお葬式と異なるため、検討する際は違いを把握しておきましょう。
この記事では、お別れの会の特徴や一般的なお葬式との違いを紹介します。

お別れの会とは、故人さまとのお別れの場として設けられる会です。
一般的にはお葬式とは別の日に改めて実施され、ご逝去された方を偲ぶために行います。宗教や宗派にとらわれることなく、自由なスタイルで執り行えることが大きな特徴です。
お別れの会の形式にも決まりはなく、故人さまの想いや故人さまらしさを大切にしたお別れの会を執り行っても問題ありません。会場の選択も自由であり、故人さまが生前好きだった趣味をテーマにした会場で執り行うケースもあります。

一般的なお葬式とお別れの会には、以下のような違いがあります。
| お葬式 | お別れの会 | |
|---|---|---|
| 目的 | 宗教儀礼 | 自由な追悼 |
| 主催者 | ご遺族 | ご遺族・友人・知人 |
| 参列者 | 故人さまの家族・知人・友人 | 故人さまとお別れしたい人 |
| 開催日 | ご逝去されて数日以内 | ご逝去されて1~2ヵ月以内 |
| 宗教 | 宗教に基づくのが一般的 | 制約されないことが多い |
それぞれの違いについて解説します。
お葬式は宗教儀礼であるのに対し、お別れの会は故人さまを偲ぶためのイベントです。
お葬式は正式な儀式であり、ご遺体もあるため、さまざまな規則が細かく定められています。一方、お別れの会は主催者の意向に基づき自由に行うことができます。そのため、お別れの会の目的も主催者によって異なるのが特徴です。
お葬式の主催者はご遺族であるのに対し、お別れの会はご遺族、友人、会社の同僚、趣味仲間などです。
お別れの会はお葬式に参列できなかった方のために、改めてお別れの場を提供するために行います。そのため、家族葬を開催して参列できなかった方のために、お葬式の主催者が改めてお別れの会を開催するケースが多いです。
また、お葬式に参列していない関係者が集まって発起人会を作って開催するケースもあります。
お葬式は故人さまの親族や友人、知人が参列するのに対し、お別れの会は身内だけのケースもあれば、故人さまとお別れしたい人が自由に参列できることもあります。
例えば、家族葬で故人さまの親族のみがお葬式を執り行った際に、お別れ会ではお葬式に参列できなかった友人や知人を広く招待する場合もあります。お葬式の規模や故人さまの交友関係により、お別れの会の参列者は大きく変わってくるのが特徴です。
お葬式は故人さまがご逝去されてから数日以内に開催するのに対し、お別れの会は開催時期に決まりはなく、いつでも行えるのが違いです。
一般的にはお葬式から約2週間〜2ヵ月程度を目安に行われ、四十九日法要や一周忌法要、故人さまの誕生日に合わせて行われることもあります。
開催時期は、ご遺族や参列者の都合を考慮し、日程に余裕を持って事前に調整する必要があります。時間的に余裕を持つことにより、故人さまと親しかった人が参列しやすくなります。
お葬式は故人さまの信仰する宗教に則って行われるのに対し、お別れの会は宗教の制約を受けない違いがあります。
お別れの会は無宗教形式がほとんどで、お葬式と違って読経やお焼香などの儀式は行わないケースが多いです。ただし、主催者の意向次第では、お別れの会でも部分的に宗教的な要素を含む場合もあります。
宗教的な要素を含む・含まない点においても、自由に決められるのがお別れの会の特徴です。

お別れの会は自由な形式で執り行えますが、主にセレモニー形式、会費制パーティー形式、法人開催形式で行われるケースが多いです。
ここでは、それぞれの開催形式の特徴を紹介します。
セレモニー形式は、一般的な告別式に近い形で開催されるお別れの会です。
会場正面には生花祭壇を飾り、参列者は祭壇の前に着席します。会によっては厳かな雰囲気で行われ、短い読経やお焼香などの宗教儀礼を含むケースも少なくありません。
式中には故人さまの経歴紹介や発起人挨拶、葬送儀礼、参列者の弔辞などを行います。最後には参列者が一人ずつ献花を行います。
会費制パーティーは、参列者が会費を支払って参加するパーティー形式のお別れの会です。
お別れの会として選ばれることが多い形式で、最初に弔礼や献花などを行い、その後は食事に移ります。食事は立食のビュッフェスタイルが一般的で、宗教的儀礼はなく、会食途中での退場や献花だけでも参加できるのが特徴です。
セレモニー形式に比べると生花祭壇は簡略化されやすく、会食中に弔辞や故人さまのエピソード紹介が行われます。
また、セレモニー形式と会費制パーティー形式を組み合わせたお別れの会が行われることもあります。
お別れの会は法人が主催者となって行う場合もあります。
例えば、企業や団体に所属する人がご逝去した場合に、組織が主体となって行う社葬・団体葬などです。
法人開催形式のお別れの会は、以前だと大企業の代表者がご逝去した際に大規模に行われることが多かったですが、最近は中小企業でも創業者や代表者が対象となるケースがあります。

お別れの会に参列する場合、会費やお香典を持参するのが一般的です。
ここでは、お別れの会の会費・香典について解説します。
お別れの会に持参するお金は、会によって会費かお香典か異なります。
お別れの会の案内状に会費が記載されている場合、会費として持参しましょう。会費を支払う場合はお香典は不要であり、お香典を持参すると主催者側が困る場合もあるため注意が必要です。
案内状に会費やお香典に関する記載がない場合はお香典を持参します。「香典辞退」と記載されている場合は、会費もお香典も不要です。
お別れの会の会費・お香典の一般的な相場は、おおむね1〜2万円程度です。
ただし、お別れの会の会費・お香典には厳密なルールがなく、故人さまとの関係性やお別れの会の規模、地域によって大きく異なります。
お別れの会で飲食がある場合は、飲食代を考慮し、お香典の金額を少し高めに設定するとよいでしょう。お別れの会に参加する予定の知人がいる場合は、相談してみるのもおすすめです。
案内状に金額が記載されている場合は、過不足なくその金額を持参しましょう。
お香典については以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
お別れの会で会費を渡す場合は、香典袋にお金を包む必要はなく、そのまま受付で支払っても問題ありません。
会費をより丁寧にお渡ししたい場合は、白無地の封筒の表に氏名、裏に住所と金額をボールペンで記載しましょう。
お香典を渡す場合は、お葬式と同様に白黒の水引を結んだ香典袋または白無地の封筒を使用します。お別れの会は宗教色が薄いため、表書きはどんな宗教にも使用できる「御香典」と記載して渡すとよいでしょう。

お別れの会はお葬式ではないため、会場選びも自由に行うことができます。
ここでは、お別れの会を行う場所を解説します。
セレモニーホールは、お葬式や法事を執り行うための施設です。
故人さまにゆかりのある会場で執り行うことにより、故人さまの供養にもつながります。宗教や宗派に関係なく、さまざまな形式のお別れの会に対応できるメリットがあります。お別れをするための設備が整っており、利便性が高く、比較的安価に利用できるのが特徴です。
一方で、収容人数や駐車場台数に限りがある点に注意する必要があります。また、セレモニーホールにはお葬式や法事のイメージが強いため、形式にとらわれない形にしたい場合は他の会場も視野に入れて判断するとよいでしょう。
ホテルは他の会場に比べると広く、同時に会食をしたい方にもおすすめです。
クロークや駐車場での誘導など基本的なサービスが充実しており、参加者への待遇面においても優れています。明るい雰囲気の中で、出席者へのおもてなしを重視したい場合に適している会場です。
一方で、一般の宿泊利用客への配慮が必要なことや、ご遺骨の安置や宗教儀礼が行えない場合もあります。また、サービスの質が高い分、利用料が高額になりやすい点にも注意が必要です。
自宅は主催者が移動せずに準備ができるため、時間的な負担を減らせるメリットがあります。
飾りつけに制限もないため、家のさまざまな場所に故人さまゆかりの写真を飾ることや、趣味の品も飾れます。
一方で、自宅でのお別れの会の場合は人数や規模に制限がかかる点に注意が必要です。また、自宅でのお別れの会は準備や片付けも主催者が行うため、負担がかかりやすくなります。駐車場のスペースや玄関の広さ、トイレの数などを考慮すると小規模な会に適しています。
多目的ホールはさまざまな種類があり、会場によっては大規模なお別れの会にも対応できます。
ホテルに比べると利用料が安価な傾向にあり、公営のホールを利用すると費用を大幅に抑えることが可能です。一方で、お別れ会での利用を想定していないホールも多く、演出には別途費用がかかりやすい点に注意する必要があります。
故人さまのスライドショーを流したい場合は、ホールに設備がなければレンタルしなければなりません。また、多目的ホールは参会者案内や駐車場案内などをするスタッフがいないため、主催者側で手配する必要もあります。
お別れの会を行う場所としてレストランも挙げられます。
誕生日やお祝いなどのイベント対応しているレストランであれば、演出に必要な機材が揃っている場合もあります。中にはお別れの会のプランがあるレストランもあるため、プランを利用すると主催者側の負担も軽減できるでしょう。
一方で、読経やお焼香を行うことやご遺骨の持ち込みはできない場合もあります。また、レストランによっては駐車場の台数が少ない場合もあります。
お別れの会を開催する場合は、段階を追って進めていくのがポイントです。
ここでは、お葬式が終わって1か月後にお別れの会を開催する場合を例として流れを紹介します。
葬儀・告別式を終えたら、お別れの会を開催する約四週間前に会場・日時を決定します。
案内状を作成し、往復はがきで故人さまの親しかったご友人等へ送付、出欠確認をとります。
お別れの会の約三週間前には、式場関係者とお別れの会の内容の打ち合わせ、飲食関係等の打ち合わせをします。
会場の下見と見積りの確認も忘れずにしておきましょう。また、出席者の確認と出席リストの作成、弔辞者の選定、依頼を行います。
お別れの会の約二週間前には、お別れの会の内容を確認します。装飾や飲食メニュー、映像、音楽内容等の演出を確認します。この時点で会の見積りを最終確認し、前受金を支払います。
お別れの会の約一週間前には、出席者の人数の最終確認、飲食物の最終発注を行います。
お別れの会を開催する一時間前くらいに主催者・ご遺族が会場に集まりリハーサル、発注品の確認を行います。
お別れの会参加者の受付をすませます。
お別れの会参加者が入場します。
参加者がお花を祭壇等に供えます。閉式の辞の前に行うこともあります。
映像や生前に好きだった曲等を演奏し、故人を回想します。
弔辞者が故人へのお別れの言葉を述べます。また、司会が弔電を読み上げます。
弔辞者が故人へのお別れの言葉を述べます。また、司会が弔電を読み上げます。
遺族代表者がお別れの会参加者へ御礼の挨拶をします。
会食を行います。参会者へ御礼の挨拶の前に行われることもあります。

お別れの会は、直葬(火葬式)と合わせて行うケースも増えています。
ここでは、お別れの会を直葬(火葬式)と合わせて行うケースが増えている理由やそのメリットを解説します。
直葬(火葬式)とは、お通夜や葬儀・告別式を行わずに行うお葬式です。
簡素なお葬式として近年増加傾向にあり、シンプルでなおかつ限られた費用で供養できます。大勢の人が集まる一般葬とは異なり、ご家族やご親族、親しい友人などで行うのが一般的です。
直葬では葬儀・告別式を行わないため、故人さまと過ごす時間も少なくなります。
ゆっくりとお別れがしたかったという場合に、おすすめするのがお別れ会です。後日、まとまった時間をとってお別れ会を催すことで悲しみを癒すことができます。
直葬については以下の記事でも詳しく解説しています。
こちらの記事を読んでいる方におすすめ

直葬とお別れ会を合わせて行うことで、費用を抑えつつ故人さまを偲べるメリットがあります。
直葬は葬儀・告別式を省略するため、他のお葬式に比べると費用が安いのが特徴です。お葬式の費用を抑えつつ、予算に応じてお別れ会を行うことで心を込めて見送れます。
お別れの会は自由に開催日を決められるため、予算に余裕ができてからお別れの会を開催するのもよいでしょう。
直葬は、ご遺族が決めるだけでなく故人さまが生前に希望しているケースもあります。
故人さまが直葬を希望していた場合は、故人さまの気持ちを優先しましょう。その際、故人さまとゆっくりお別れの時間を取ることができないため、落ち着いてからお別れの会を検討するのもおすすめです。

ここでは、お別れの会でのよくある質問を紹介します。
お別れの会は、お葬式とは別に故人さまとお別れする場として設けられる会です。
お別れの会は比較的自由なイベントであり、故人さまのご意向に沿って開催される場合もあります。自由度が高い一方で、会によってはある程度のルールが設けられている場合もあるため、参列する場合は事前に確認することが大切です。
また、開催する側になった場合には、日程や会場の調整も必要となります。不安やわからないことがある場合は、葬儀社に相談してみるのもよいでしょう。
お葬式のことなら、「よりそうお葬式」にご相談ください。
よりそうお葬式では専門相談員が24時間365日いつでも無料でご相談を受け付けています。お葬式にまつわるご不安によりそい、サポートいたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。
※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

葬儀の種類・宗派
神式のお葬式で知っておきたい香典袋のマナーは?参列時のマナーや作法を紹介

葬儀の種類・宗派
一般葬とは?参列者の範囲やメリット・デメリットなどを解説!

葬儀の種類・宗派
死装束は好きな服を選べる?注意点や宗派ごとの違いを解説

葬儀の種類・宗派
一日葬とは?5つのメリットと3つのデメリットを詳しく解説!
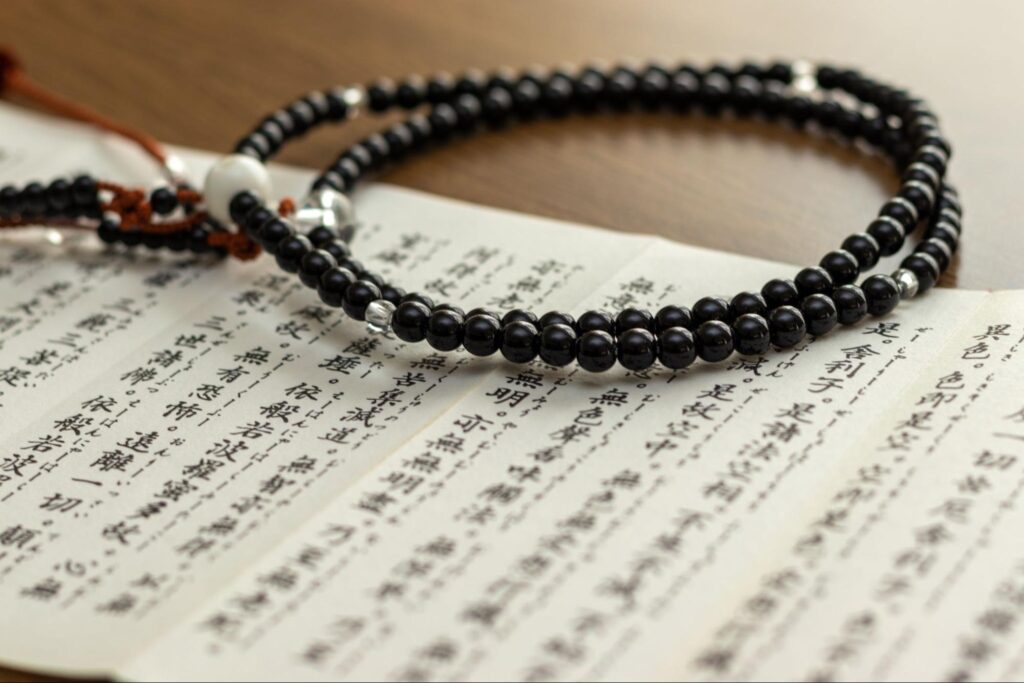
葬儀の種類・宗派
浄土真宗のお経の由来は?宗派や葬儀におけるマナーについて解説

不動明王とは?真言の唱え方や効果などについて

これで安心!お坊さんの呼び方の種類を押さえよう!

13宗派56派の宗祖・教え・教典・唱名など

祈祷とは?祈願との違いはなに?意味や流れについて解説

般若心経の内容全文と解説まとめ|知れば心が楽になる「空」の思想

二礼二拍手一礼による参拝の流れは?行う理由や例外を解説
横にスクロールできます

一日葬とは?5つのメリットと3つのデメリットを詳しく解説!

一般葬とは?参列者の範囲やメリット・デメリットなどを解説!

寺院とのつきあいが負担になってきた?檀家のやめ方

菩提寺についてよくわからない人のための基礎知識

浄土宗ってどういう信仰?葬儀の特徴やマナーは?

禅宗の1つ!臨済宗の特徴と葬儀の流れを徹底解説!
横にスクロールできます