
-
葬儀のマナー
-
意外に知らないお通夜の持ち物!マナーはあるの?

お亡くなりになった故人さまのお身体を一時的に保管することを、ご遺体安置といいますが、具体的にどのように対応すれば良いのかわからない人もいらっしゃるでしょう。
故人さまのお身体は、ご遺体安置室と呼ばれる場所で保管するのが通例です。
この記事では、ご遺体安置室とは、種類、搬送方法、安置方法、儀式、注意点について詳しく解説します。
身内にもしものことがあったものの、どのように対応すれば良いのかわからない人は、ぜひ当記事を参考にしてみてください。

ご遺体安置とは、ご臨終からお葬式の日まで決められた場所にご遺体を保管することです。
死亡判定を受けてから、ご遺体をご自宅もしくは安置施設に移します。病院の霊安室や警察署の霊安室では長い時間ご遺体を安置しておくことはできません。
そのため、ご遺体の安置場所や搬送方法は、お葬式の詳細を決める前に決めておく必要があります。

ご遺体安置室とは、文字通り故人さまのお身体を安置するための場所です。ここでは、ご遺体安置室について詳しく解説します。
ご遺体安置室とは、故人さまのお身体を一時的に保管するための場所のことです。
仮に病院でお亡くなりになった場合、病院の安置室で、厳重に保管されます。
ただし、病院での安置は一時的で数時間〜1日程度しか保管できないため、その後、自宅や葬儀社などに搬送する必要があります。
ご遺体安置室は、自宅の部屋・葬儀社・民間施設など比較的自由に選べますが、どう対応すれば良いかわからない人は取り急ぎ葬儀社に相談するのが安心ではないでしょうか。
安置室と霊安室は字面が似ていますが、別物です。
安置室は故人さまのお身体をお葬式までの間、一時的に保管する場所とされるのに対して、霊安室は安置室に移動するまでの間、一時的に利用される場所となります。
どちらも似ている言葉ではあるものの、順番としては霊安室⇒安置室となるわけです。
霊安室は数時間程度と短時間ですが、安置室ではお葬式までの間の数日間にわたって保管できます。
日本の法律では、ご逝去後24時間は火葬できないとされているため、お葬式を執り行うまでの間は霊安室ではなく安置室で保管すると覚えておきましょう。
ご遺体安置に関しては葬儀社がすべて対応しているため、お亡くなりになったタイミングで相談しておいてください。

ご遺体安置室は、一時的に病院で保管してもらうことが可能ですが、ずっと保管してくれるわけではないため、必要に応じて自宅の部屋・葬儀社・民間施設への搬送が必要です。
ここでは、ご遺体安置室の種類について詳しく解説します。
故人さまが病院でお亡くなりになった場合、一時的に霊安室で安置されます。
厳密には霊安室に一時的に保管しておき、数時間後に他の安置室に移動させるという手順となるのですが、病院のスタッフが対応してくれる分、何かと安心です。
あくまでも一時的な対応となるため数時間で搬送が必要となりますが、病院でお亡くなりになった場合は医師や看護師が対応してくれるため、わからないことは聞いておくと良いでしょう。
故人さまのお身体を搬送する場合、自宅の部屋という選択肢があります。
自宅の部屋で安置するとなると何かと不安が尽きないように思えますが、あくまでもお葬式までの間の保管となるため、過度に心配する必要はありません。
葬儀社に相談すれば、ドライアイスを使用した基本的な防腐処理を行ってもらえます。特別な防腐処理であるエンバーミングを希望する場合は、別途対応可能か確認しましょう。
自宅の部屋をご遺体安置室とすることも珍しくないため、まずは葬儀社にご相談ください。
故人さまがお亡くなりになった場合、真っ先に相談すべきなのが葬儀社です。
葬儀社は故人さまのお身体の搬送はもちろん、その後のお葬式の手配などもすべて行っているため、タイミングを見計らって相談しておくことを推奨します。
状況によってはすぐに対応できないこともありますが、大抵の葬儀社は常に対応できるよう準備しているため、もしもの際にはまず葬儀社に相談しましょう。
緊急時にも即対応してくれるため、何かあれば迷わず連絡するのが望ましいです。
なお、葬儀社によっては複数のプランを用意しているため、ご遺体安置のタイミングでお葬式の規模や形式についても話し合っておくとより安心といえます。
ご遺体安置に関しては、一部の民間施設で行われていることも珍しくありません。
業者によってどのような対応なのかは変わってきますが、24時間対応で面会制限がないところがあるため、葬儀社が決まるまでの繋ぎとして利用するのが良いです。
自宅にスペースがない場合や葬儀社が予約で埋まっている場合でも、民間施設によってはすぐに対応してくれることがあります。
利用できる施設が限られている点や費用面を考えると、葬儀社と比べ利便性は劣りますが、慎重に葬儀社を選びたい方には役立つ選択肢です。
故人さまのお身体の保管に必要なものを揃えてくれるため、役立つサービスの一つとして知っておいて損はありません。

ご遺体の搬送は葬儀社への依頼、搬送先の選択、搬送先への移動というのが基本の流れです。
ここでは、ご遺体の搬送方法について詳しく解説します。
故人さまのお身体を搬送する場合、葬儀社に依頼するのが一般的です。
例外的に自力でご遺体を搬送することも可能ですが、現代では葬儀社に依頼して運んでもらうのが主流といえます。
葬儀社に依頼すれば、ご遺体安置に慣れているスタッフが中心となって運んでくれるため、途中でトラブルに見舞われることもありません。
自力での搬送は何かと問題が発生しやすいため、特別な理由がない限りは葬儀社に依頼すると良いでしょう。
なお、以下の記事ではご遺体搬送の流れや費用について解説しているため、あわせて参考にしてみてください。
こちらの記事を読んでいる方におすすめ こちらの記事を読んでいる方におすすめ

葬儀社に依頼する場合、搬送先を選択することとなります。
搬送先は基本的に自宅または葬儀社の安置室となるため、希望する方を選択してください。特別な要望がない場合は、葬儀社の判断に任せましょう。
なお、葬儀社がなかなか決まらない場合は、民間施設に依頼するのも一つの方法です。
葬儀社はご遺体安置だけでなくお葬式に必要な儀式の手配などを迅速に行ってくれますが、業者によってプランが変わってきます。
プランによっては一般葬の他に家族葬や火葬式(直葬)が行えるところもあるため、慎重に判断したい人もいらっしゃるでしょう。
その場合は、一時的に民間施設で保管してもらいつつ、葬儀社を比較検討すると良いです。
最終的に、指定した搬送先への移動を行えば、ご遺体安置は完了です。
なお、お葬式までの間、故人さまのお身体は適切に保管するのはもちろん、季節によっては腐敗することがあるため、防腐処理が必要となる場合があります。
大抵は、葬儀社に依頼すればエンバーミングと呼ばれる防腐処理を行ってくれるため安心ですが、業者によって対応方法が変わることもあるため、注意が必要となるでしょう。
ご遺体を安置する期間は、一般的に2日〜3日程度とされています。
ただし原則日本の場合、火葬以外は許可がおりず、火葬場の休日や予約状況によりご遺体の安置期間が長くなることもあります。
基本的に火葬場のお休みは友引と元日です。
民間の火葬場の場合、お正月の三が日をお休みとしているところもあります。
なお、日本の場合は法律で24時間以内の火葬は禁止されているため、必ず1日以上安置することになります。
これは、仮死状態が見落とされたということが前例としてあるためです。

ご遺体の安置方法は、宗教や宗派によって変わることがあるため、注意が必要です。
ここでは、ご遺体の安置方法について詳しく解説します。
仏式のご遺体の安置方法は、以下の点にご注意ください。
仏教では、故人さまのお身体を安置する場合、枕の向きは北枕にするのが一般的です。
顔に白い布を被せて両手を組むようにし、枕元には白い布を被せた台を置きます。
最後に、枕飾りとして一膳飯・花瓶・香炉・燭台・鈴・線香・枕団子・水などを飾れば、仏式のご遺体安置は完了となります。
神式のご遺体の安置方法は、以下の点に注意しましょう。
神道では、故人さまのお身体を安置する場合、基本的に枕の向きは西枕または東枕にします。
頭の付近には八足の机を置き、必要に応じて御札や霊代を飾ると良いです。
最後に、枕飾りとして榊・塩・洗米・水などを飾れば、神式のご遺体安置は完了です。
一部、キリスト教では独自のご遺体安置が行われることがあります。
基本的にキリスト教は宗教や宗派によって故人さまのお身体をどのように扱うか変わるわけではありませんが、特別な理由がなければ枕の向きは北枕にするのが一般的です。
キリスト教には枕飾りなどの慣習はありませんが、十字架・聖書・ろうそくなどを置く場合があるため、どうすれば良いかわからない場合は葬儀社にご相談ください。
なお、一部の宗教や宗派によっては独自の方法で対応することもあるため、古くからのしきたりや習わしを重んじる場合は地元の年長者に聞いてみましょう。

ご遺体安置後は、末期の水(まつごの水)、清拭(せいしき)、湯灌(ゆかん)、着替え、死化粧、納棺を行うのが通例です。
末期の水とは、故人さまの口元に水を含ませる儀式です。
別名で死に水とも呼ばれ、故人さまが安らかに旅立てるようにとの思いが込められています。
故人さまの口元に水を含ませるようになった経緯については諸説あるものの、口を湿らせることで死の苦しみから解放されると信じられてきたのが由来とされています。
従来はお亡くなりになる直前に行われていましたが、現代はご逝去後に行うのが通例となりました。
具体的な方法としては、ガーゼや脱脂綿などに水を含ませ、喪主や配偶者など故人さまとの関係性がある人の手で湿らせるのが通例です。
清拭とは、故人さまのお身体をタオルなどで拭いて綺麗にする儀式です。
お葬式を執り行うにあたって可能な限り清らかな状態を保つのが目的で、主に葬儀社のスタッフによって行われます。
なお、エンバーミングと呼ばれる防腐処理も行われることがあります。
本来、故人さまのお身体は短時間しか保存できませんが、エンバーミングを施すことによって長時間の保存が可能となるため、あわせてやってもらうと安心です。
湯灌とは、故人さまのお身体をお湯で洗って清潔にする儀式となります。
生前の穢れを落として来世への旅立ちを願う他、死後硬直を和らげて納棺しやすくする目的があるとされています。
なお、湯灌は湯灌師と呼ばれる人が対応し、必要に応じて洗顔や洗髪も行います。
無精髭が生えている場合は、カミソリで剃って身支度を整えてくれるため、何か別途で要望がある場合は湯灌師に伝えておくと安心です。
ご遺体安置後は、お葬式に備えて着替えも必要となるでしょう。
着替えも葬儀社のスタッフが対応してくれるため、施主が自ら対応することはありません。むしろ、故人さまのお身体は不慣れな人が扱うと損壊することがあるため、プロに任せるのが良いでしょう。
ご遺体安置後は、死化粧と呼ばれるメイクも行われます。
死化粧とは、故人さまの顔や髪を整え、化粧を施すことです。
故人さまが安らかに眠っているように見せるのが目的ではありますが、生前の姿に近づけることで本人の尊厳を守る目的もあるといえるでしょう。
化粧によって身支度を整えることで、ご遺族の気持ちを癒すのにもつながります。
死化粧はご家族やご親族が対応しても構いませんが、不慣れな場合はプロに任せるのが安全です。
最終的には納棺を行い、完了です。
納棺とは、故人さまのお身体を棺に納める儀式となります。
お葬式の前に近親者が集まって執り行う儀式で、故人さまが愛用していた品や思い出の品を入れて、あの世への旅立ちに備えます。
なお、湯灌、着替え、死化粧などをまとめて納棺の儀とする場合もあるため、葬儀社に確認しましょう。

ご遺体安置中は、いくつかの注意が必要です。
ここでは、ご遺体安置中の注意点について詳しく解説します。
ご遺体安置中は、故人さまには直接触れないようご注意ください。
死化粧をしたりする際に若干触れることはありますが、慣れない人が故人さまのお身体に直接触れるとあざや傷ができる場合があります。
一度できたあざや傷はなかなか消せないため、直接触れるのは避けるべきです。
室温を適切に管理するのは、ご遺体安置中の鉄則です。
過度に暖めると腐敗が進んでしまう可能性があるため、室温は18度以下を目安にし、ドライアイスなどによる冷却を行いましょう。
ご遺体を安置する場合、寝具は白で統一するのが基本です。
白で統一する理由は、汚れがない色であるからだと考えられています。白色であれば、生前に使用していた寝具をそのまま使っても問題ありません。ただし、洗ったばかりのシーツやカバーをかけて清潔感を保ちましょう。
白色の寝具がない場合は薄い色のもので代用しても問題ありません。
また、ご遺族がお亡くなりになった季節が寒い冬でも厚い布団をかけるのはNGです。厚い布団をかけると腐敗が進む可能性があるため、薄い寝具を用いなければなりません。
導線を十分に確保するのも、ご遺体安置中の鉄則といえます。
ご家族やご親族が何度も行き来する場所に安置するとぶつかってしまう可能性があるため、邪魔にならない場所での保管が必要です。
ご自宅でご遺体安置を行う際には、ドライアイスを首や下腹部にあてて腐敗を遅らせる必要があります。
ご遺体の安置期間は短くても1日、人口の多い首都圏になると2~3日が一般的です。火葬場の予約状況によっては、それ以上の安置が必要になるケースもあります。
ご遺体の状態を生前に近い状態で保つためには、お亡くなりになった直後から冷却しなければなりません。特に故人さまの体が大きかったり、体温が高かったりする場合は冷却を急ぐ必要があります。
ドライアイスを首に置くのは顔の周辺が変色するのを防ぐためです。下腹部にあてるのは腐敗が内臓から進みやすいことや、冷たい空気が下に伝わるため、体全体を効率よく冷やすためです。
ただし、死因やご遺体の状態によっては冷やすべき部位の優先順位が異なる場合もあります。ドライアイスの設置には専門知識が必要ですが、基本的には葬儀社のスタッフが行ってくれるため心配は不要です。
故人さまがお亡くなりになってからお葬式までの間、ご遺体を安置する際に枕元に枕飾りを準備します。
枕飾りとは故人さまの魂があの世に旅立ち、成就できるように願うために行うものです。体から離れた魂がこの世にすがり、憑りつくことを防ぐための役割もあります。
仏教の場合だと、小さい机に白い布をかけるか、白木の机を用意して以下のものを並べるのが一般的です。
香炉には線香を1本立てて、燭台にはろうそくを立てます。花立てにはユリや菊の花を飾り、枕団子を6個(地域によっては11個)を飾るのがしきたりです。
一膳飯は故人さまの茶碗にご飯をつぎ、中心に箸を2本立てます。
なお、焼香と燭台と花立てのセットを三具足(みつぐそく)といい、祭壇を作るうえで必要な道具です。地域によっては燭台と花立てを一対にし、五具足とする場合もあります。
宗教による違いもあり、浄土真宗では枕団子や枕飯、水は飾りません。
ご遺族で枕飾りを用意する場合は、どのようなお供え物を用意すればいいか葬儀社や菩提寺に確認しましょう。お葬式の準備などでご遺族の負担も大きいため、葬儀社に依頼して用意することもできます。
ご遺体を安置する際に、故人さまの胸元に置く短剣のことを守り刀といいます。
守り刀は刃の刃先がお亡くなりになった故人さまの顔に向かないように、刃先は足元に向けるのが基本です。掛け布団の上から胸元におき、納棺したあとは棺桶の上に置きます。
実際に用いられる刀は本物とは限りません。銃刀法に抵触しないように、模造刀を使用するのが一般的です。また、剃刀や小刀、ハサミ、木刀が使用される場合もあります。
守り刀の風習は全国各地で古くから行われているもので、その由来に定まった説はありません。仏教や神式、民間信仰など、それぞれの宗教の考えと結びついて説明されます。
例えば、仏教の場合だと、お亡くなりになった故人さまが極楽浄土に渡るためのお守りという説です。神式は亡くなることを穢れとする考えがあり、穢れを払うために刀が用いられているという説もあります。
人によっては、ご遺体安置中に面会を求められることがあるため、誰が来ても対応できるよう備えておくのが良いでしょう。
葬儀社によっては面会できる時間に制限を設けていたり、別途で料金がかかったり、そもそも面会不可だったりすることもありますが、訪れてくれた人には真摯な対応が望ましいです。
自宅で安置している間は、施主の判断で面会を許可するかどうか判断できるため、必要に応じて準備しておくことを推奨します。
なお、単純に忙しかったり悲しみで対応できそうになかったりする場合は、面会をお断りしても問題はありません。
あくまでも面会に対応するかどうかは、ご遺族と話し合って判断しましょう。
ご遺体安置室は、故人さまのお身体を保管しておくための場所です。
故人さまがお亡くなりになってから24時間はご火葬ができないため、病院の霊安室だけでなく葬儀社や民間施設の安置室を利用することになります。
もしくは自宅で保管することになるため、どう対応すべきか知っておくと良いでしょう。
なお、お葬式を執り行うのが初めてで何から着手すれば良いかわからない場合は、最初から最後まで任せられるよりそうお葬式にご相談ください。
当社では一般葬の他に家族葬や火葬式(直葬)など、複数のプランをご用意しています。また、よりそうでは、ご自宅や葬儀社の安置施設など、希望に合った選択肢をご用意しています。
プラン自体はアレンジが可能なため、柔軟に対応可能です。
もし葬儀社がまだお決まりでない場合は、ぜひ一度当社の公式ホームページをご覧ください。
「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。
※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

葬儀のマナー
意外に知らないお通夜の持ち物!マナーはあるの?

葬儀のマナー
お通夜に持参する香典のマナー!

葬儀のマナー
お通夜とは?意味やマナーを徹底解説!

葬儀のマナー
お通夜と告別式の違いは?どちらに参列すべき?知っておきたいポイントや参列マナーを紹介

葬儀のマナー
お通夜での挨拶マナー!立場別に紹介

【訃報の連絡で使える文例付き】訃報のお知らせの意味と書き方

通夜・葬儀、喪服でのハンカチは何色?男女の違いは?お葬式の持ち物マナー

身内の不幸の職場への連絡はメールで大丈夫?忌引きメールのマナーを解説

香典をいただいた時の言葉やマナーとは?お礼の伝え方やメールを送る場合の書き方を解説

淋し見舞いとは?書き方と渡し方

友達の親が亡くなった時にかける言葉は?参列の判断基準や対応方法を紹介
横にスクロールできます
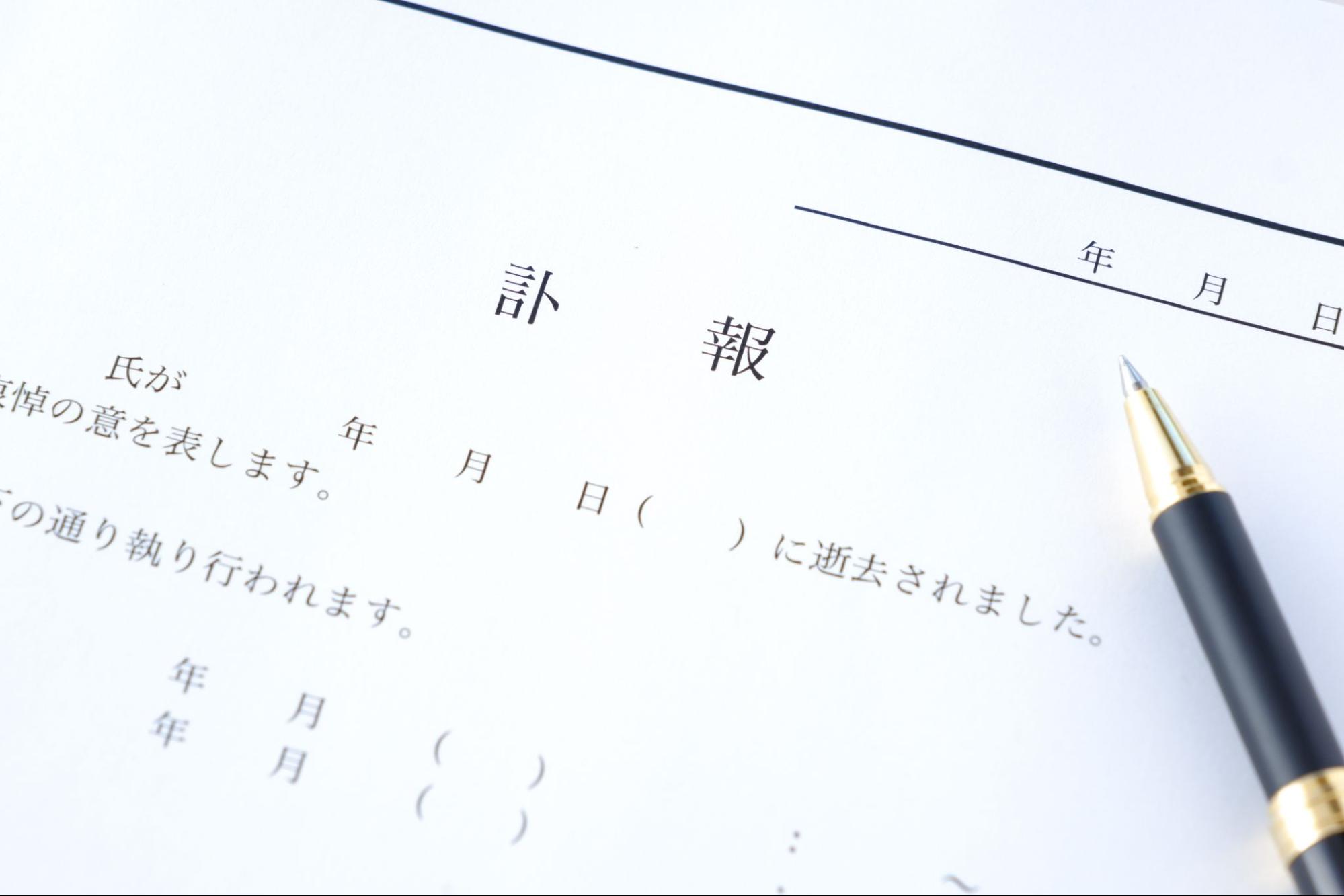
お葬式の連絡はいつする?相手・注意点・方法・例文を解説

一周忌に用意するものは?喪主側と参列者側でそれぞれ解説

香典返しはいくらが目安?適切な金額をケース別に紹介

意外と知らない?弔電の宛名や宛先に関するマナーまとめ

お通夜とは?意味やマナーを徹底解説!

お通夜と告別式の違いは?どちらに参列すべき?知っておきたいポイントや参列マナーを紹介
横にスクロールできます