
-
葬儀のマナー
-
意外に知らないお通夜の持ち物!マナーはあるの?

お葬式がダメな日は具体的に法律で定められているわけではありませんが、一部の宗教・宗派では友引(ともびき)の日を避けるという考え方があるため、注意が必要です。
友引とは、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口からなる六曜(ろくよう)の一つで、お葬式の日取りの参考とされることが珍しくありません。
この記事では、2025〜2026年分の友引カレンダー、ダメとされる理由、重なった場合の対処法、日程を組む方法、友引以外のお葬式にまつわる風習について詳しく解説します。
お葬式のダメな日をカレンダー形式で紹介するため、ぜひ参考にしてみてください。

お葬式がダメな日は具体的に法律で定められているわけではないものの、一部の宗教や宗派によっては友引を避けるのが通例です。
ここでは、お葬式がダメな日はあるかについて詳しく解説します。
お葬式に関しては、具体的にダメな日というのはないとの認識で良いでしょう。
あくまでも考え方の一つとして友引は避ける傾向にありますが、家庭や地域によってはいつどこでお葬式をやっても良いと考えるところもあります。
縁起の良し悪しよりも故人さまの弔いを優先したい場合は、あまり日取りを気にしなくても問題ないです。
一部の宗教や宗派によっては、友引は避けるという考え方があります。
そもそも友引とは何かというと中国から伝わった考え方で、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口という六つの組み合わせによって毎日の吉凶を占うものです。
具体的な意味については、以下を参考にしてください。
よくカレンダーで見るのが、以上の六つです。
このなかにある一つが友引であり、日本ではお葬式を避けるべき日とされています。
もちろん、必ずしも友引を避けなければいけないというわけではありませんが、家庭や地域によっては避けなければならないと考えているところもあるため、十分注意しましょう。
なお、友引のお葬式が縁起が悪いとされていることについては以下の記事でも解説しているため、あわせて参考にしてみてください。
ここからは、吉凶を左右する六曜について詳しく解説します。
六曜は厳密にはお葬式と関係ありませんが、気になる方はご覧いただけますと幸いです。
六曜とは、日付や時間帯の吉凶を左右する暦の一種です。
原型は中国で作られたもので、日時や方角などをもとに物事の吉凶を占う「暦注(れきちゅう)」の1つとされています。
中国では古くから暦を活用した占いが行われており、六曜以外にも「干支(えと)」や「九星(きゅうせい)」などがあります。六曜はこうした暦注の一つです。
よくカレンダーで目にする「友引」「仏滅(ぶつめつ)」「大安(たいあん)」などは、この六曜の考え方からきたもので、冠婚葬祭の際に気にする方は少なくはありません。
日本では、古来より縁起の良し悪しやゲン担ぎで六曜を気にする場合が多いです。
ただし、お葬式においては必ずしも六曜に合わせるという決まりはなく、各々の予定に合わせて行えば問題ありません。
六曜として挙げられる日は、次の通りです。
| 六曜の項目 | 意味 |
|---|---|
| 先勝 | 午前は吉で午後からは凶だが、勝負事には吉日とされる |
| 友引 | 朝は吉だが昼は凶となり午後から大吉とされ、弔事では凶日とされる |
| 先負 | 午前は凶で午後からは吉だが、勝負事には凶日とされる |
| 仏滅 | 午前・午後とも凶日で祝事・慶事は避けるべきだが、仏事には問題ない日とされる |
| 大安 | 午前・午後とも吉日で祝事・慶事に適している日とされる |
| 赤口 | 午前11時〜午後1時までは吉、それ以外は凶とされ、慶事は大凶とされる |
六曜には決められた順番があり、「先勝→友引→先負→仏滅→大安→赤口」という流れで回っています。
もともと六曜は旧暦で特定の周期ごとにやってくるとされていましたが、現代では新暦が採用されているため、不規則な割り当てとなっています。
そのため、お葬式を執り行う際には友引がいつくるかの事前確認が必要です。
友引でもお葬式は可能ですが、火葬場によっては休業日となっている場合もあるため、事前に確認しておくことを推奨します。
なお、友引以外であればいつお葬式を挙げても問題はありません。

お葬式がダメな日に決まりはありませんが、友引などを避けたい場合は、2025年・2026年の友引カレンダーで把握しておくと安心です。
ここでは、お葬式がダメな日がわかる友引カレンダーについて詳しく解説します。
2025年の月ごとの友引の日は、以下のようになっています。
| 月 | 友引の日 |
|---|---|
| 1月 | 2日(木)、8日(水)、14日(火)、20日(月)、26日(日)、30日(木) |
| 2月 | 5日(水)、11日(火)、17日(月)、23日(日)、28日(金) |
| 3月 | 6日(木)、12日(水)、18日(火)、24日(月) |
| 4月 | 3日(木)、9日(水)、15日(火)、21日(月)、27日(日) |
| 5月 | 2日(金)、8日(木)、14日(水)、20日(火)、26日(月)、30日(金) |
| 6月 | 5日(木)、11日(水)、17日(火)、23日(月)、27日(金) |
| 7月 | 3日(木)、9日(水)、15日(火)、21日(月)、27日(日) |
| 8月 | 2日(土)、8日(金)、14日(木)、20日(水)、24日(日)、30日(土) |
| 9月 | 5日(金)、11日(木)、17日(水)、22日(月)、28日(日) |
| 10月 | 4日(土)、10日(金)、16日(木)、26日(日) |
| 11月 | 1日(土)、7日(金)、13日(木)、19日(水)、24日(月)、30日(日) |
| 12月 | 6日(土)、12日(金)、18日(木)、23日(火)、29日(月) |
以上の友引カレンダーを参考にしておけば、もしものことがあっても安心です。
2026年の月ごとの友引の日は、以下のようになっています。
| 月 | 友引の日 |
|---|---|
| 1月 | 4日(日)、10日(土)、16日(金)、21日(水)、27日(火) |
| 2月 | 2日(月)、8日(日)、14日(土)、18日(水)、24日(火) |
| 3月 | 2日(月)、8日(日)、14日(土)、19日(木)、25日(水)、31日(火) |
| 4月 | 6日(月)、12日(日)、22日(水)、28日(火) |
| 5月 | 4日(月)、10日(日)、16日(土)、21日(木)、27日(水) |
| 6月 | 2日(火)、8日(月)、14日(日)、18日(木)、24日(水)、30日(火) |
| 7月 | 6日(月)、12日(日)、16日(木)、22日(水)、28日(火) |
| 8月 | 3日(月)、9日(日)、14日(金)、20日(木)、26日(水) |
| 9月 | 1日(火)、7日(月)、11日(金)、17日(木)、23日(水)、29日(火) |
| 10月 | 5日(月)、16日(金)、22日(木)、28日(水) |
| 11月 | 3日(火)、13日(金)、19日(木)、25日(水) |
| 12月 | 1日(火)、7日(月)、12日(土)、18日(金)、24日(木)、30日(水) |
以上の友引カレンダーのように、曜日による吉凶は毎年変わるため注意が必要です。

友引のお葬式は、火葬場が休みとなる点、字面が不吉である点、六曜を重んじる点などから避けられるのが一般的です。
基本的に絶対ダメというわけではありませんが、気になる場合は避けるのが良いでしょう。
ここでは、友引のお葬式がダメとされる理由について詳しく解説します。
友引の日は、多くの火葬場が定休日に設定しています。
いくらお葬式をしたくても火葬場が休みであれば少なくともご火葬はできないため、必然的に避けるパターンとなります。
故人さまがお亡くなりになった翌日や翌々日が友引の場合、お葬式を執り行う日取りの調整が必要となるでしょう。
なお、火葬場は友引以外にも元旦を含む年末年始が休みとなることもあるため、火葬場の都合によってお葬式ができない日があるという点は理解しておく必要があります。
どうしてもお葬式と友引が被る場合は、友引人形を使用して対応すると良いです。
友引は字面が不吉である点から、お葬式には適さない日とされています。
友を引くと書くため、故人さまがご友人をあの世に連れていくと考えられるわけです。
ゆえに、友引の日にお葬式をするのは縁起が悪いため、避けるのが良いとされているのです。逆に、結婚式などのおめでたい場ではかえって友引の方が縁起が良いとされます。
あくまでも縁起の良し悪しの話にはなるものの、日取りを決める場合の参考にしておくと気持ち的に楽ではないでしょうか。
日本では、六曜を重んじる人も珍しくありません。
六曜は中国から伝わった考え方ですが、日本のカレンダーにも記載されるほど浸透しており、祖父母や両親から友引の日のお葬式はダメと教わってきた人もいらっしゃるかと思います。
生活のなかで今日は仏滅だ、明日は大安だと考えることは稀ですが、冠婚葬祭では参考にする人も多いです。
少なくとも六曜という考え方自体は日本でも重んじられる場合があるため、お葬式などでは特に地元の葬儀社や年長者と相談して日取りを決める必要があるでしょう。

友引の日にお葬式を執り行う場合は、友引人形を棺に入れる、もしくは日程を先送りにするのが良いです。
ここでは、友引とお葬式が重なった場合の対処法について詳しく解説します。
お葬式と友引の日が重なる場合、友引人形を棺に入れるのが良いでしょう。
友引人形とは、友引の日にお葬式を行うにあたって、故人さまがご友人をあの世に連れて行ってしまうのを防ぐために身代わりとして棺に納める人形のことです。
関東地方ではあまり目にしない風習ですが、関西地方ではよく行われる風習となっています。
友引人形は葬儀社に相談すると用意してくれる場合がある他、本人が生前愛用していたぬいぐるみなどを代わりに納めることでも対応可能です。
どうしても友引の日とお葬式が被る場合は、友引人形をご活用ください。
友引の日にお葬式をしなければいけない場合、日程を先送りにする方法もあります。
そもそも故人さまがお亡くなりになってから24時間はご火葬ができないため、1〜2日経過してからお葬式をすることになります。
もし故人さまの命日の翌日が友引の場合、お葬式を1日先送りにすると良いでしょう。ご遺族や参列者の都合によっては、翌々日の2日先送りにするのも良いのではないでしょうか。
通常、お身体の安置期間は2〜3日とされているため、3日前後までであれば調整可能です。
故人さまの安置は葬儀社が対応するのが一般的であるため、依頼する葬儀社とよく相談しながら決めるとより安心できます。
お葬式の日取りを決める際は、いくつかの注意が必要です。
ここからは、お葬式の日取りを決める際の注意点を詳しく解説します。
お葬式の日取りを決める際は、方法によって必要な日数が変わる点に注意が必要です。
火葬式(ご火葬とご収骨のみのお葬式)のように、お通夜や告別式を省くお葬式は1日で終わりますが、一般葬はお通夜・告別式・ご火葬で2日かかります。
お葬式の形式によって必要となる日数が変わるため、日取りを決める際にはどの方式でお葬式を執り行うのかをあらかじめ決めておく必要があるでしょう。
故人さまがお亡くなりになった後、24時間はご火葬ができません。
これは法律で定められているもので、かつて「蘇生の可能性があった時代の名残」です。現代では医学の発展により、息を引き取ったかどうかは医師によって判断されます。
そのため、蘇生の判断で間違うことはないでしょう。
しかし、法律で「死亡後24時間は火葬してはならない」とされているため、お葬式は翌日以降となります。
火葬式の場合は1日空けてから行わなくてはならないため、日取りに注意が必要です。
友引は、火葬場が定休日の場合があります。当然ながら火葬場がお休みだった場合はご火葬ができないため、注意が必要です。
火葬場にも定休日がある他、状況によっては焼却施設のトラブルによって対応できない場合があるため、お葬式の日取りを決める際は火葬場のスケジュールも確認しましょう。
友引の前後は読経の依頼が集中するため、日取りに注意が必要です。
友引の日は火葬場がお休みとなる場合が多いことから、友引の前後に読経を依頼する人も少なくありません。
結果的に日取りが思うようにいかないパターンもあるため、友引の前後はスケジュールの調整が必要となります。
友引の前後は葬儀場も混雑するため、日程調整に注意が必要です。
友引の日は火葬場のお休みに合わせてお葬式を執り行う人が集中するため、結果的に葬儀場そのものが混雑します。
場合によっては他のお葬式で葬儀場が埋まってしまう可能性もあり、スケジュールの調整がやや難しいです。そのため、友引の前後は早めの予約が必要となります。

お葬式の日程はある程度調整ができるため、意図的に友引を避けることが可能です。
ここでは、友引を避けてお葬式の日程を組む方法について詳しく解説します。
まずは、お坊さんの都合をご確認ください。
仏式のお葬式はお坊さんがいないと執り行えないため、お坊さんの都合を確認します。古くからお世話になっている菩提寺(ぼだいじ)がある人は、菩提寺に都合を確認すると良いです。
お坊さんの都合がついたら、火葬場の空き状況を確認します。
火葬場が満杯になることはそうそうありませんが、お亡くなりになる人が偶然にも重なった場合、近場の火葬場が予約で埋まりやすいです。
年間の死亡者数に対して火葬炉の数が限られているため、場合によっては対応できないこともあるでしょう。営業時間も限られているなど、空き状況によっては待ちが発生することも珍しくありません。
お坊さんの都合がついても火葬場が空いていないとお葬式はできないからこそ、うまく日程を調整できるようにしておくと良いでしょう。
火葬場の都合がついたら、参列者の状況も確認すべきです。
参列者によっては遠方にいてすぐに駆けつけられなかったり、仕事で来られなかったりするため、どれくらいの人が参列できるのかをある程度予想しておく必要があります。
参列者の状況によって予約する葬儀場の規模や形式も変える必要があるため、ご家族やご親族を含めどれほどの人が参列できるのか予測しておくと良いのではないでしょうか。
家庭や地域によっては独自の風習が残っているところもあるため、あわせて確認しましょう。
身内のなかには友引を絶対に避けたいと考える人もいるため、お葬式の日取りを決める場合は一度相談してから決めるのが安心です。
お葬式の手配は主に施主が行いますが、極力全員で話し合っておくと後々のトラブルを避けられます。

お葬式に関しては友引以外にも色んな風習があり、一部の家庭や地域では古くからの迷信として信じられているものもあるため、いくつか把握しておくと安心です。
ここでは、友引以外のお葬式にまつわる風習について詳しく解説します。
一部の家庭や地域では、妊婦がお葬式に参列する場合、鏡をお腹に向けて忍ばせることがあります。
妊婦がお葬式に参列すると、赤ちゃんが霊に連れていかれるといわれたり、あざのある赤ちゃんが生まれるといわれたりするため、未だにお腹に鏡を入れることもあるそうです。
一般葬のように1日目にお通夜、2日目に葬儀・告別式・ご火葬を執り行う場合、参列者は葬儀場などに宿泊するケースがあります。このとき、北枕では眠らないように注意しましょう。
北枕は、仏式のお葬式で故人さまを寝かせる姿勢で、縁起が悪いとされます。
一部地域では、火葬場の行き帰りは違う道を通る風習があります。
なぜ火葬場の行き帰りは違う道を通るのかというと、故人さまの霊がご家族やご親族と一緒に家まで戻ってきてしまうことを防ぐためです。
故人さまが迷わずに成仏できるよう、あえて自宅の場所をわからなくさせるという風習であるため、注意が必要となります。
その他には、以下のような迷信が残っています。
以上の二つは、どちらも親の死に目に会えなくなるのを防ぐためのものです。
日本では古くから夜に爪を切ったり、霊柩車を見ても親指を隠さなかったりすると親の死に目に会えなくなるといわれています。
あくまでも迷信ではあるものの、人によっては古くからの教えが染みついている人もいるため、念のため注意しておくと良いでしょう。
他にも独自の迷信が信じられていることがあるため、気になる人は地元の葬儀社や年長者に相談しておくと安心です。
お葬式がダメな日は法律などで定められているわけではありませんが、六曜の一つである友引に執り行うのは避けるのが一般的です。
もし身内にもしものことがあった場合は、友引を避けてお葬式を手配します。
基本的には友引にお葬式をしても問題ないとされるものの、身内によっては反対する人もいる他、火葬場が休みだったり字面が不吉だったりするため、避けるのが良いでしょう。
どうしても友引にお葬式が必要な場合は、日程を先送りにしたり、友引人形を入れたりして対応しましょう。
なお、お葬式の手配が必要な場合は、よりそうお葬式にご相談ください。
当社ではお通夜・葬儀・告別式・ご火葬まですべて対応できる一般葬はもちろん、身内だけで執り行える家族葬、シンプルにご火葬のみを行う火葬式(直葬)にも対応しています。
ご要望やご予算に合わせて柔軟に対応できるのはもちろん、複数のプランがある他、アレンジにも対応可能なため、まずは一度ご相談いただけると幸いです。
「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。
※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

葬儀のマナー
意外に知らないお通夜の持ち物!マナーはあるの?

葬儀のマナー
お通夜に持参する香典のマナー!

葬儀のマナー
お通夜とは?意味やマナーを徹底解説!

葬儀のマナー
お通夜と告別式の違いは?どちらに参列すべき?知っておきたいポイントや参列マナーを紹介

葬儀のマナー
お通夜での挨拶マナー!立場別に紹介

【訃報の連絡で使える文例付き】訃報のお知らせの意味と書き方

通夜・葬儀、喪服でのハンカチは何色?男女の違いは?お葬式の持ち物マナー

身内の不幸の職場への連絡はメールで大丈夫?忌引きメールのマナーを解説

香典をいただいた時の言葉やマナーとは?お礼の伝え方やメールを送る場合の書き方を解説

淋し見舞いとは?書き方と渡し方

友達の親が亡くなった時にかける言葉は?参列の判断基準や対応方法を紹介
横にスクロールできます
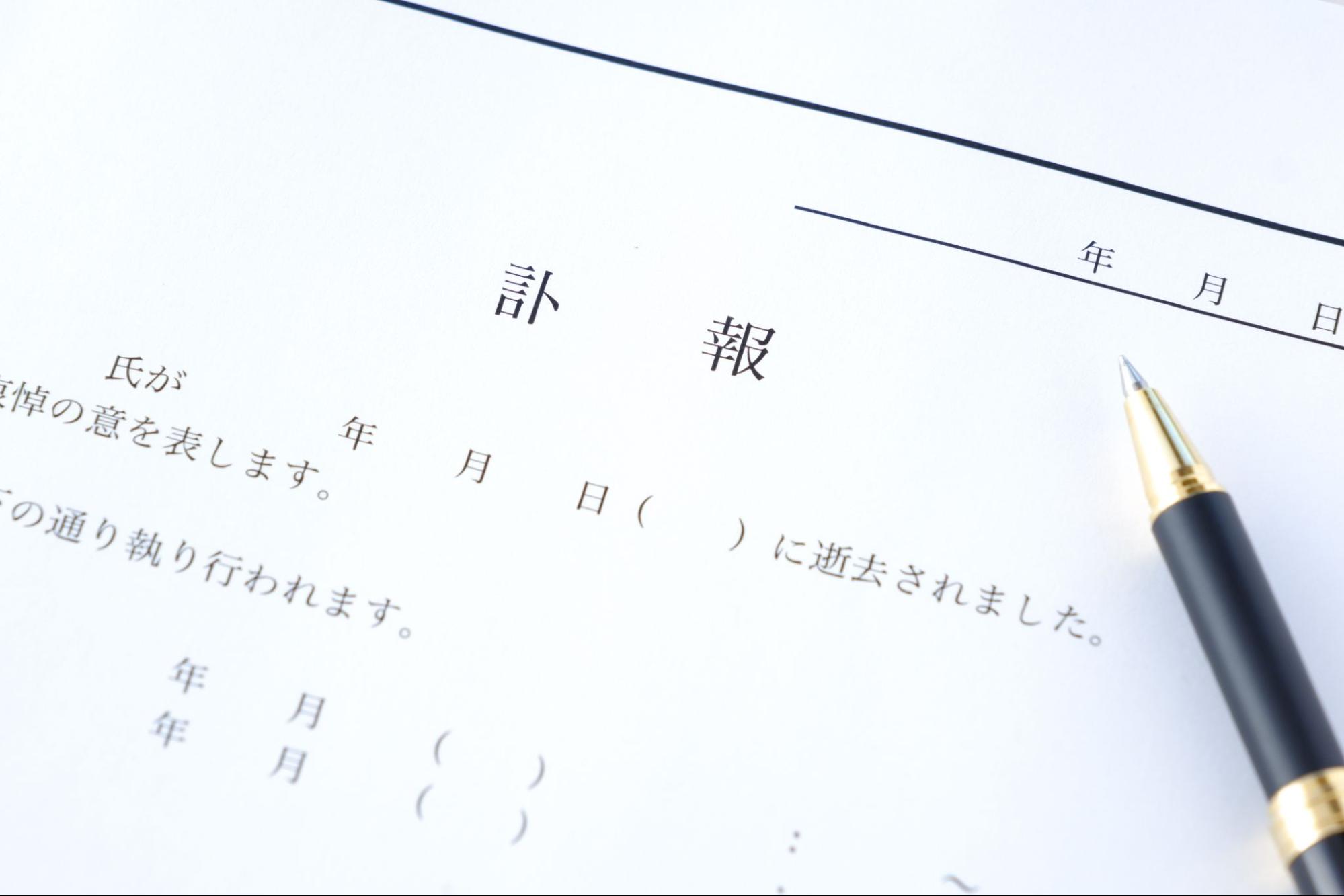
お葬式の連絡はいつする?相手・注意点・方法・例文を解説

一周忌に用意するものは?喪主側と参列者側でそれぞれ解説

香典返しはいくらが目安?適切な金額をケース別に紹介

意外と知らない?弔電の宛名や宛先に関するマナーまとめ

お通夜とは?意味やマナーを徹底解説!

お通夜と告別式の違いは?どちらに参列すべき?知っておきたいポイントや参列マナーを紹介
横にスクロールできます