
-
葬儀のマナー
-
意外に知らないお通夜の持ち物!マナーはあるの?

訃報を受け、通夜の開始時間に間に合いそうもないということがあるかと思います。
通夜と葬儀があるけど仕事で遅刻してしまう、葬儀に遅刻してしまうなど、通夜に遅刻してしまうときは、葬儀のマナーとしてどうすることが最適なのでしょうか。
地域や宗教・宗派のしきたりによって違いがある場合もありますが、ここでは一般的な通夜に遅刻する場合のマナーについて説明します。

最近では、通夜と葬儀を一緒に行う1日葬や家族葬というのも増えています。
葬儀や告別式に遅刻というのは気が引けるものですが、急なご不幸でも参列したい間柄なのに、どうしても通夜に間に合わない…、葬儀に仕事で遅刻する…、という場合がないとは言い切れません。
そんな時にどうしたらよいのでしょうか?
結論からお伝えしますと、遅れそうな場合でも、通夜への遅刻が30分から1時間程度であれば、あきらめず参列しましょう。
告別式や葬儀の時間に遅刻するのは基本的にはないことが普通ですが、「通夜は遅れてでも駆けつけるのがマナー」です。
ご遺族の方にしてみれば、たとえ遅刻してしまったとしても、忙しい中、故人のために駆けつけてくれたということはとてもありがたいことです。
通夜の開始時間は午後6~7時が一般的です。
このため、通夜が平日の場合は、仕事終わりにそのまま駆け付ける方も多くおられますし、仕事の都合上、葬儀に間に合わないという場合も少なくないと思います。
ご遺族が会場や部屋を借りている時間の関係もありますので、何時まで弔問が可能かに関しては、通夜が斎場で開かれている場合は、斎場に問い合わせると良いでしょう。
もし、借りている時間を過ぎてしまうと斎場自体に入ることができなくなってしまいますので、注意が必要です。また、キリスト教の場合は、通夜の儀式が終わってしまうと、誰もいなくなってしまいます。
通夜が終わった後も親族などが食事やお茶などを頂いている時間は約1時間から1時間30分程度が一般的です。
なお、遅れた際には、遅れたことに対してのお詫びを伝えることを忘れないようにしましょう。
通夜への弔問は、故人との関係性(友人、会社の上司、同僚等)によっても変わりますが、一般的には、親族や親しい間柄、もしくは会社関係の場合に伺います。
故人との関係性を考えると、遅くなっても弔問したいという気持ちが強いケースが多いとは思いますが、遅過ぎる時間の弔問は避けることをお勧めします。
遅い時間と一言に言っても通夜の時間によって異なります。
親族でない場合は、18時から19時が開始の時間の場合、20時くらいまでは通夜ぶるまいしていることが多いですが、到着するのが20時以降になる場合、故人や遺族との関係が深いのであれば遅れることを事前に連絡して参列するのが良いでしょう。

故人やご遺族との関係が深くなく到着が20時以降になる場合や、たとえ関係が深くても22時を過ぎる場合は、無理に通夜に参列することは避け、翌日の葬儀に参列するか、葬儀が終わった後に訪問するようにしましょう。
親族の場合も、到着が大幅に遅れてしまう場合は、事前に旨を連絡し、時間が許す限り駆けつけます。ご遺族の方々が待たれていることがありますので、急遽行けなくなってしまった場合も必ず連絡をしましょう。
通夜に遅刻に関しての疑問や質問を下記にまとめました。 一般的な回答となりますが、参考にしてください。
一般的な通夜の流れは、僧侶の読経〜お焼香〜通夜ぶるまいとなります。
30分程度の遅れなら焼香に間に合います。
どうしても遅刻してしまう場合は、僧侶の読経の間は入室せず、読経が終わり、お焼香が始まってから入室します。
そして、受付の人に案内してもらい、最後列に座り、焼香が始まったら参列された方々と一緒にお焼香させていただきましょう。
通夜とは、故人を偲ぶために執り行われるものです。
遅刻はマナー違反にはなりませんので、できる限り出席するようにしてください故人への思いをご遺族の方々にお伝えするためにも、遅刻をしても出席することをお勧めします。

ただし、通夜ぶるまいは宴席ではないので、個人とは関係のない話題に夢中になったり、お酒を飲んで長居するのはNGです。また、途中で退席する場合は、周囲の人に「お先に失礼します」と述べてから静かに退席するようにしてください。
基本的に通夜が執り行われている時間内の遅刻連絡は不要です。
通夜が始まると、関係者は参列と弔問客の対応に忙しくなるためです。
折角連絡をしても、葬祭場の場合、自宅の場合どちらの場合も喪主やご遺族の方への連絡は式が終わってからとなる可能性が高いためです。
通夜の日は、ご遺族にとっても忙しいため、遺族に直接電話を入れることはマナー違反です。
もし、斎場に連絡を入れていたにも関わらず、ご遺族の方々にその旨が伝わっていなかった場合でも、遺族は余裕がないことも多いため決して腹を立てないようにしましょう。
なお、どうしても連絡をしたい場合は、マナーとしても、通夜の最中ではなく、始まる前に連絡するようにしましょう。
通夜が始まる前ですと、係の方からご遺族の方にも伝わりやすいです。
時間によってはご遺族の予定にも影響を与えてしまい、迷惑になることもあります。
到着時間が大幅に遅れる場合や通夜の後になる場合には、通夜の最中であっても斎場に連絡をいれて、到着予定時間をお伝えし、弔問に伺っても支障がないか確認をしましょう。
通夜ぶるまいとは、弔問に対するお礼とお清め、個人の供養のために設けられており、ご遺族と弔問客が、故人の思い出話などをしながら食事をする場、いわゆる「故人を偲ぶ会」です。
以前は、通夜のお手伝いや対応で忙しくして、お腹が空いているお手伝い頂いた方やご遺族の方に、少しでもお腹に入れられるようおにぎりやお茶を振る舞うことを「通夜ぶるまい」と呼んでいましたが、現在は、弔問に来てくださった方々全員に振る舞うのが一般的となっています。
通夜ぶるまいに誘われたときは、たとえ通夜に遅刻していても「受けるのが礼儀」です。誘われたときは遠慮せずに席につき、一口でも箸をつけるようにしてください。
訃報は突然受ける事も多いものなので、仕事や予定を繰り合わせても、日時や距離によっては、遅刻してしまうことも無くはありません。
しかし、このページで紹介したように、「通夜は遅れてでも駆けつけるのがマナー」です。
つまり、何よりも大切なことは、通夜は故人を偲び、別れを惜しむために参列するものだということです。
通夜は急なことなので、通夜の遅刻は決してマナー違反とはなりません。
ただ、気をつけておくこととしては、伺う時間によっては、ご遺族の方々に負担をかけてしまうということです。
通夜が執り行われている場所によっても異なりますが、ご遺族への心遣いを忘れず、弔問することをお勧めします。
「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。
※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

葬儀のマナー
意外に知らないお通夜の持ち物!マナーはあるの?

葬儀のマナー
お通夜に持参する香典のマナー!

葬儀のマナー
お通夜とは?意味やマナーを徹底解説!

葬儀のマナー
お通夜と告別式の違いは?どちらに参列すべき?知っておきたいポイントや参列マナーを紹介

葬儀のマナー
お通夜での挨拶マナー!立場別に紹介

【訃報の連絡で使える文例付き】訃報のお知らせの意味と書き方

通夜・葬儀、喪服でのハンカチは何色?男女の違いは?お葬式の持ち物マナー

身内の不幸の職場への連絡はメールで大丈夫?忌引きメールのマナーを解説

香典をいただいた時の言葉やマナーとは?お礼の伝え方やメールを送る場合の書き方を解説

淋し見舞いとは?書き方と渡し方

友達の親が亡くなった時にかける言葉は?参列の判断基準や対応方法を紹介
横にスクロールできます
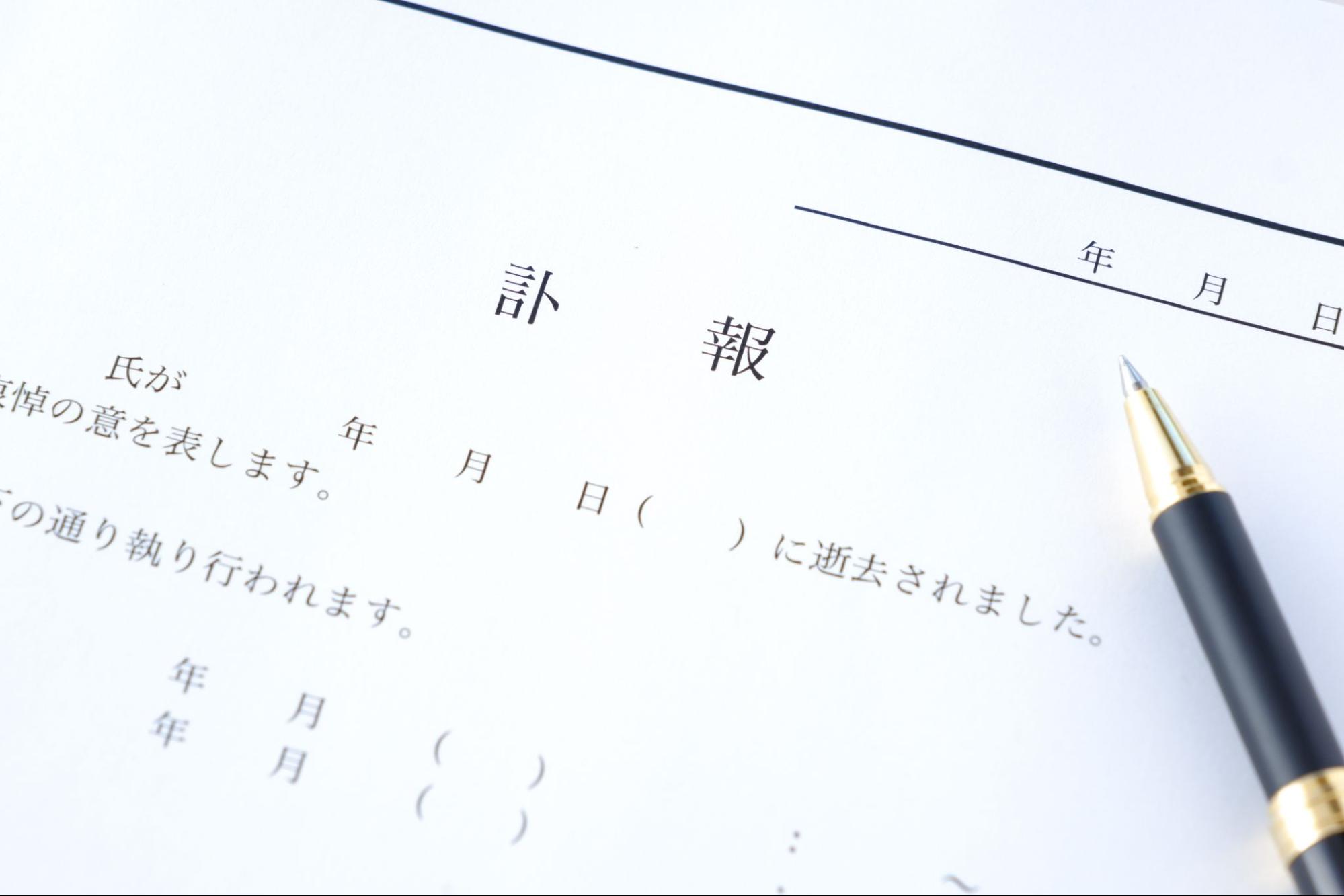
お葬式の連絡はいつする?相手・注意点・方法・例文を解説

一周忌に用意するものは?喪主側と参列者側でそれぞれ解説

香典返しはいくらが目安?適切な金額をケース別に紹介

意外と知らない?弔電の宛名や宛先に関するマナーまとめ

お通夜とは?意味やマナーを徹底解説!

お通夜と告別式の違いは?どちらに参列すべき?知っておきたいポイントや参列マナーを紹介
横にスクロールできます