
-
葬儀のマナー
-
意外に知らないお通夜の持ち物!マナーはあるの?

祖父・祖母のお葬式に参列する際、「孫としてどのようなことができるか」と考える方もいるでしょう。
小さい頃からお世話になってきた祖父・祖母とのお別れは悲しいものです。
後悔のないお見送りをするためにも、お亡くなりになったときにできることや、マナーを知っておきましょう。
この記事では、大切な祖父や祖母がお亡くなりになったときにやるべきことやマナー、注意点などを詳しく紹介します。

祖母・祖父がお亡くなりになったと連絡があった場合、どのように対応したらよいのでしょうか。ここでは、連絡があった場合にするべきことを紹介します。
祖母・祖父のお葬式に参列する場合、会社に忌引きの連絡を入れましょう。連絡手段は口頭、もしくは電話が望ましいです。
まずは、口頭や電話で休むことを伝えたうえで、可能であればメールを送りましょう。メールを送って文字に残しておくと、休暇申請を処理する担当者も見返せます。
メールを送る際は、休暇の申請期間やお葬式に関する内容など、必要な情報を伝えましょう。
また、深夜や早朝のように電話が難しい場合もメールで伝えます。この場合は、改めて電話連絡を入れて、休暇の手続きや引き継ぎのお願いなども直接しておきましょう。
祖父や祖母のお葬式に参列する際、会社によっては忌引き休暇があります。忌引き休暇とは会社の福利厚生の一環で、弔事の際に会社を休める制度のことです。
忌引き休暇は企業が独自に設けている制度であるため、企業によって詳細が異なる点に注意しましょう。
企業によって名称が異なっており、喪に服すという意味の慶弔休暇としているところもあります。また、忌引き休暇中に給料が出るかどうかは、企業が定めたルール次第です。
忌引き休暇の期間が単なる欠勤扱いになる場合もあれば、有給休暇と同じように出勤日数に含まれていることもあります。
雇用形態によっても変わる場合があるため、事前に企業の就業規則を確認しておきましょう。
祖父や祖母のお葬式に参列できない場合は、弔電で弔意を伝えましょう。
孫という立場上、祖父や祖母の家族から訃報の連絡が届く場合も多くあります。その際に参列できないことを伝え、さらに弔電で弔意を伝えるのがマナーです。
遠方に住んでいたり、病気や体調不良だったりなど、お葬式に参列できないケースもあります。感染症を考慮し、親族でもお葬式への参列を控える場合もあるでしょう。
そもそも弔電とは、お葬式に参列できないときにお悔やみの言葉を送る電報のことです。電話やインターネットを通じて、簡単に弔電を送ることができます。
お通夜か告別式のどちらかに参列できる場合、弔電を送る必要はありません。

弔電はどのように送ったらよいのでしょうか。ここでは、弔電を送る流れと注意点を紹介します。
弔電を送る際、基本的に送り先は葬儀場で宛名は喪主です。弔電を送るにあたって、必要となる情報を調べておく必要があります。
お届け先となる葬儀場名と住所を確認し、その情報に間違いがないかもチェックしておきましょう。
また、弔電は喪主名で送るため、訃報を受けた際には故人さまだけでなく、喪主のフルネームもしっかり確認しておくことが大切です。
弔電は、お通夜か告別式の数時間前までに届くように送るのがマナーです。できればお通夜までに相手の手元に届くのが望ましいでしょう。
しかし、お通夜に間に合いそうにない場合は無理に間に合わせる必要はなく、翌日の告別式に間に合うように送れば問題ありません。
弔電をお届けした際に、親族不在で届かない場合や、葬儀場で受け取りができないケースもあるため注意しましょう。
何かの手違いで弔電を届けられない場合は、親族に連絡を取ったうえで祖父・祖母の家を訪問します。
ただし、弔問に出向くことは、孫とはいえお葬式後のさまざまな対応に追われる親族に迷惑をかける可能性もあるため、事前連絡を入れることが大切です。
弔電では、特有の敬称が使われる点に注意する必要があります。また、敬称は故人さまと喪主との関係性によって変わるのも特徴です。
例えば、喪主が叔父で祖父がお亡くなりになった場合、喪主から見ると父親となります。弔電では実父について、お父上やご尊父様と呼びます。
このケースだと故人さまが自分の祖父であっても、お祖父様と呼ぶのは間違いです。
ただし、自分の親や祖母が喪主を務めるような関係性が近いケースだと、お父上やご尊父様と呼ぶと他人行儀な印象を与えてしまいます。
そのため、親しみを込めて「おじいさま」「おじいちゃん」としても問題ありません。
弔電を送る際には忌み言葉に気をつけましょう。忌み言葉とは、一般的に特定のシーンや不幸、不吉なことを連想させる言葉を指します。
忌み言葉は以下が挙げられます。
また、宗教によっても避けるべき言葉があります。例えば、仏教では「迷う」「浮かばれない」などは避けた方がいい言葉です。
弔電を送る際には、忌み言葉に気をつけましょう。

祖父や祖母のお葬式には基本的に参列すべきですが、それより遠い親戚のお葬式は無理に参列する必要はありません。
訃報は予期せぬタイミングで起こることが多く、他の予定や仕事の関係でお葬式の参列が難しい場合もあるでしょう。
そのため、血縁関係が遠く、普段から交流がほとんどない親戚のお葬式には、必ずしも参列しなければならないわけではありません。
血縁関係だけでみると、お葬式に参列するのは叔父や叔母、姪、甥などの三親等までが目安となります。
ただし、それより血縁関係が遠くても生前から交流がある場合は参列した方がよいでしょう。

祖母・祖父のお葬式では、親族からお手伝いをお願いされる場合もあります。お葬式は親族も準備で大変な状況にあるため、可能な限りお手伝いするのがよいでしょう。
ここでは、祖母・祖父のお葬式で手伝うことを紹介します。
孫が成人している場合、祖母・祖父のお葬式で受付をお願いされることがあります。
受付はお葬式に参列した方を出迎え、芳名帳に記入してもらってお香典を預かったり、返礼品を渡したりなどを行う係です。
お葬式の受付は、葬儀社や葬儀場のスタッフが行うのではなく、ご遺族が信頼できる人に依頼するのが一般的となっています。
お葬式の受付係には、以下のような役割があります。
このようにお葬式の受付係の業務は多岐にわたりますが、具体的に何をやるかどうかは喪主や葬儀社のスタッフの指示に従えば問題ありません。
不安を感じる場合は、葬儀社のスタッフにやるべきことを聞いて整理しておくと安心です。
祖母・祖父のお葬式では、成人している孫が会計係を任されることもあるでしょう。
会計係はお香典などの現金を取りまとめ、集計や管理などの業務を行います。また、香典を受け取って内容を確認し、誰からどれくらいの金額をいただいたかの確認も必要です。
お香典は葬儀社のスタッフが受け取れないため、ご遺族が管理をしなければなりません。
祖母・祖父の配偶者や子どもはお葬式の準備や挨拶で忙しく、血縁関係が近い孫が会計を行う場合もあります。
また、小規模にお葬式を執り行う際は受付係と会計係を兼務する場合もあります。
お葬式では、孫が接待係をお願いされる場合もあります。
接待係とは、弔問客やお坊さんの接待を行うことです。具体的には、駐車場から葬儀場、控室までの案内や荷物持ち、お茶・お菓子を出すことも挙げられます。
自宅でお葬式を行う際には、接待係が食事を作ることもあります。昔からのしきたりや地域の風習が残っている場合は、限られた時間の中で効率よく準備をしなければなりません。
また、接待係はお葬式が終わった後の法要でも引き続き接待を行う場合もあります。その場合は、祖父・祖母の家と孫の家の近さも重要になるでしょう。
お葬式の規模やお手伝いをする人がどれくらいいるかによって、具体的なお手伝い内容は変わります。
お葬式では、祖父・祖母のお葬式で駐車場の管理を任される場合もあります。
駐車場係は、弔問客の車を駐車場に案内するのが仕事です。駅から会場までの順路を案内する場合もあります。
お葬式によって交通に支障を与える可能性がある場合は、警察に道路使用許可の申請を行わなければなりません。
なお、自宅でお葬式を執り行う際に駐車場が足りない場合、駐車場の手配が必要になる可能性もあります。
進行係はお葬式の進行を滞りなく進める係で、葬儀社が行うのが一般的ですが、親族が行う場合もあります。
孫が成人して動きやすい状況にあれば、進行係を託される場合もあるでしょう。進行係の具体的な内容は以下の通りです。
進行係を任された場合は、頭で整理するだけでなく台本を作って紙にまとめておきましょう。
進行をスムーズにするためには、弔電を確認しておく必要もあります。内容はもちろんのこと、名前の漢字や読みも確認しておくことが大切です。
祖母・祖父のお葬式に参列する場合はマナーを守りましょう。ここでは、参列する前に知っておきたいお葬式のマナーを紹介します。
お葬式に参列した経験が少ないと、お葬式全体の流れがわからず、慌ててしまう可能性もあります。
故人さまを偲び、スムーズにお葬式を進めていくためにも、まずはお葬式の流れを把握しておきましょう。
お葬式に参列する際、遅刻はマナー違反となるため注意が必要です。時間と会場を事前にしっかりと確認しておいてください。
また、親族としてお葬式のお手伝いを依頼されている場合、もしくは依頼される可能性がある場合は、斎場に1時間前には入っておきましょう。
通夜振る舞いでは、孫は基本的に参加するのがマナーです。
通夜振る舞いとは、お通夜のあとに設けられる食事会のことをいいます。喪家がお坊さんや弔問客に対して感謝の気持ちを示したり、故人さまを偲んだりするのが目的です。
通夜振る舞いは、食事にお箸をつけることが供養になるとされています。そのため、食欲がなくても一口でも頂くのが礼儀です。
また、通夜振る舞いを自宅で行う場合、親族は料理を作ったり、片づけたりなど慌ただしく動かなければなりません。
そのような状況を見かけた場合は、他の参列者と話し込んだりせず、孫として手伝えることはないか親族に聞きましょう。
精進落としは、初七日法要やご火葬後に行われる会食のことで、故人さまの孫も参加するのが一般的です。
精進落としはお坊さんやお葬式の参列者、親族など、お葬式でお世話になった方々に対するお礼を目的としています。
本来、精進落としは仏教の教えに基づき、肉や魚を避けた精進料理を出すのが一般的でした。現在は風習が薄れてきており、刺身やお寿司、懐石料理を出すケースもあります。
孫として精進落としに参加する場合は、くつろぎすぎたり飲みすぎたりせず、接待で忙しい親族のサポートを行うことも大切です。
孫が祖父や祖母のお葬式に参列する際、服装は男性・女性ともに和装もしくはブラックフォーマルが基本です。
ブラックスーツの場合、男性はネクタイや靴下もブラックに統一しますが、ネクタイピンは装飾にあたるため着用は避けましょう。
女性はストッキングもブラックで統一し、メイクはナチュラルにするのがマナーです。なお、和装の喪服は第一礼装であり、お葬式の場で誰もが着るものではありません。
一般的にご遺族と呼ばれる喪主や親族が着用しますが、故人さまの二親等にあたる孫も和装を着用することは可能です。その場合は、親族に確認しておくとよいでしょう。
また、孫が学生の場合は制服での参列がマナーとなります。孫が乳幼児で制服がない場合は、ブラックを基調とした私服でも問題ありません。
ここでは、祖父・祖母を含めた親戚のお葬式に参列する場合によくある疑問や質問をまとめています。
この記事では、祖母・祖父がお亡くなりになった場合のお葬式に関するマナーや注意点を紹介しました。
孫から見た場合、祖母・祖父は兄弟姉妹と同じ二親等にあたります。何か特別な事情や、喪主の判断で呼ばない場合を除き、孫もお葬式に参列した方がよいでしょう。
家族葬においても、参列者の範囲に明確な決まりはないものの、一般的には故人さまの二親等までが参列するものと考えられています。
また、孫がお葬式に参列する際には親族からお手伝いをお願いされる場合もあるため、時間の許す限り手伝いましょう。
よりそうお葬式では、専門相談員が事前の準備からお葬式のお手配まで、お葬式にまつわるご不安によりそいサポートします。
お葬式についてわからないことがあったり、不安に感じたりする場合は、お気軽にご相談ください。
「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。
※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

葬儀のマナー
意外に知らないお通夜の持ち物!マナーはあるの?

葬儀のマナー
お通夜に持参する香典のマナー!

葬儀のマナー
お通夜とは?意味やマナーを徹底解説!

葬儀のマナー
お通夜と告別式の違いは?どちらに参列すべき?知っておきたいポイントや参列マナーを紹介

葬儀のマナー
お通夜での挨拶マナー!立場別に紹介

【訃報の連絡で使える文例付き】訃報のお知らせの意味と書き方

通夜・葬儀、喪服でのハンカチは何色?男女の違いは?お葬式の持ち物マナー

身内の不幸の職場への連絡はメールで大丈夫?忌引きメールのマナーを解説

香典をいただいた時の言葉やマナーとは?お礼の伝え方やメールを送る場合の書き方を解説

淋し見舞いとは?書き方と渡し方

友達の親が亡くなった時にかける言葉は?参列の判断基準や対応方法を紹介
横にスクロールできます
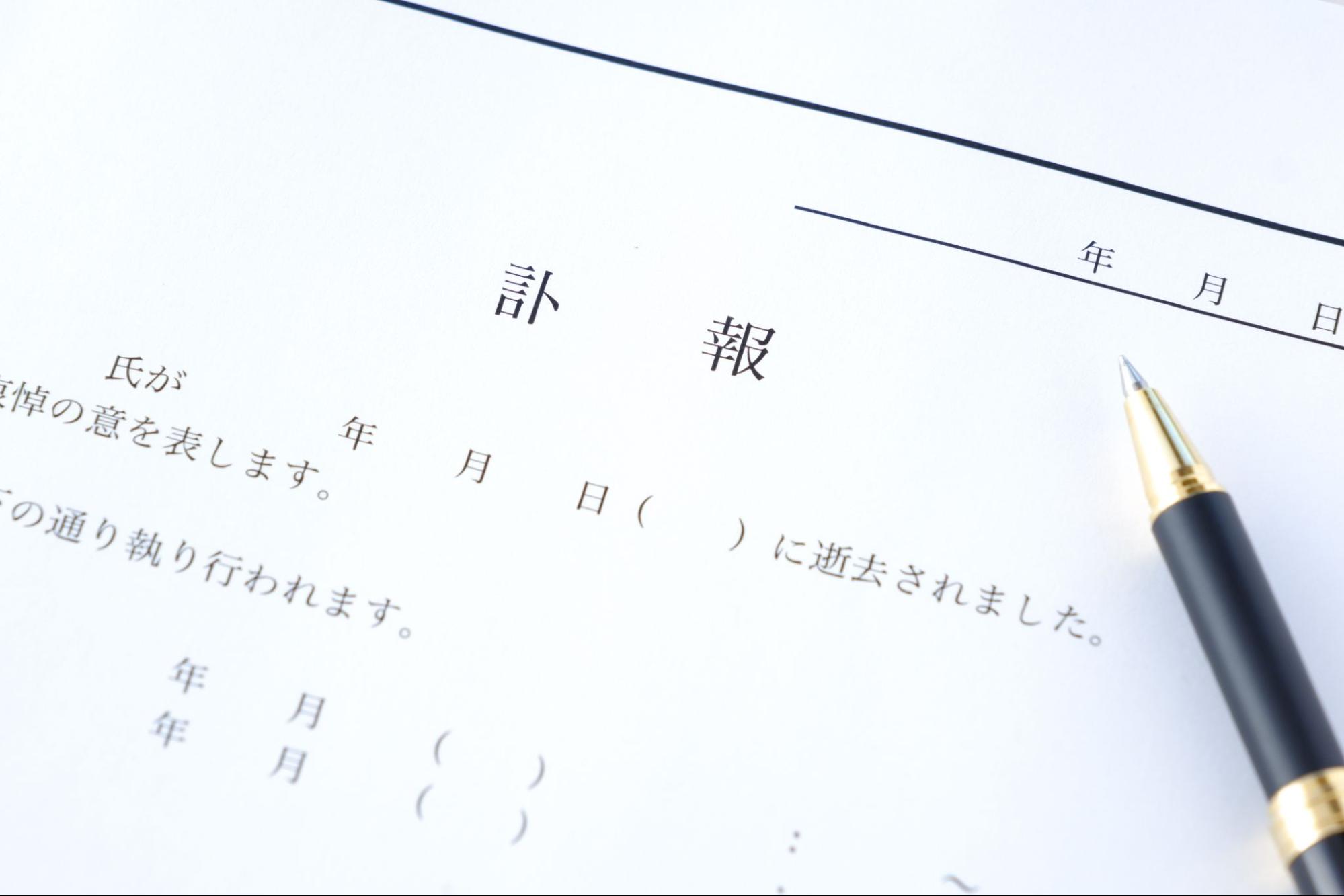
お葬式の連絡はいつする?相手・注意点・方法・例文を解説

一周忌に用意するものは?喪主側と参列者側でそれぞれ解説

香典返しはいくらが目安?適切な金額をケース別に紹介

意外と知らない?弔電の宛名や宛先に関するマナーまとめ

お通夜とは?意味やマナーを徹底解説!

お通夜と告別式の違いは?どちらに参列すべき?知っておきたいポイントや参列マナーを紹介
横にスクロールできます