
-
葬儀の流れ
-
お通夜の時間・流れの解説!始まりから終わりまで

故人とのお別れの際に行う風習に、末期の水という儀式があります。亡くなった方の唇に水を含ませている光景を見たことがある方もいるでしょう。
日本のお葬式では昔から行われている風習ですが、その意味や具体的な手順など知らない方も多いのではないでしょうか。
近しい方の臨終直後は混乱し、落ち着いて作法の確認をするのはなかなか難しいものです。いざという時に、故人の安らかな旅立ちを願い心をこめて行えるよう、あらかじめ知識を入れておくことも大切です。
ここでは、末期の水の意味や作法、注意点などについてご紹介します。
末期の水とは、息を引き取った故人の口元を水で潤す儀式です。「死に水をとる」と言われることもあり、日本の葬式文化の中で、古くから宗派を問わず広く浸透している風習です。
読み方は「まつごのみず」であり、「まっきのみず」ではないので、言い間違えないよう気をつけましょう。
末期の水の由来は諸説ありますが、お釈迦様の入滅に関する説が有力とされています。
入滅、つまり自身の最期を悟ったお釈迦さまが口の渇きを訴えた際に、信心深い鬼神が水を捧げ、これによりお釈迦様は安らかに入滅できたという逸話です。
この逸話が受け継がれ、死に行く者に喉を潤して安らかに旅立ってほしいとの想いや、生き返ってほしいという願いが末期の水にこめられるようになりました。
末期の水を行うタイミングは、かつては臨終間際でしたが、現在では臨終後に親族で行うのが一般的となっています。
病院で死亡宣告を受けた直後、もしくは故人が自宅に帰った後に行われることが多いです。故人の身体を拭き清める「清拭」や死化粧の前に行われる、最も始めの儀式です。一般的には次のような手順で行います。
末期の水をとる順番は、故人との血縁が濃い順となります。配偶者もしくは喪主から始め、故人の子、故人の親、故人の兄弟姉妹、子の配偶者、故人の孫とするのが一般的です。
葬儀に参列する際は、自分の順番を確認しておきましょう。
末期の水の儀式に必要な道具は、故人が病院で亡くなった場合は病院の方が準備をしてくれることがありますが、病院以外で儀式を行いたい場合は喪主が用意する必要があります。
ガーゼもしくは脱脂綿、新しい割り箸、お椀、顔拭き用の布があれば問題ありません。
葬祭用品として末期の水セットを用意している葬儀社もあるので、困った時は葬儀前に相談しましょう。
末期の水は、故人との最後のお別れの儀式であり、安らかに旅立てるようにと願いを込めて行われます。そして、見送る側の家族が故人の死と向き合い、受け入れるための最初の儀式ともいえます。
普段の生活では縁のない風習ですが、意味を知っていると身近な方が亡くなった際に死への向きあい方が変わってくるのではないでしょうか。
儀式を行うタイミングや手順などを理解していると、いざという時にスムーズに執り行えるでしょう。故人の生前の労をねぎらい、心をこめて行いましょう。
「よりそうお葬式」では、無料の資料をご請求いただいた方全員に「お葬式読本」を無料で贈呈しています。はじめての喪主でも安心の役立つ情報がそろっています。もしも時のための事前準備に活用できます。
※本記事の情報正確性等につきましては、細心の注意を払っておりますが、いかなる保証もするものではありません。特に宗教、地域ごとの習慣や個別の事情によって考え方や対応方法が異なることがございます。掲載情報は、ご自身の責任と判断においてご利用ください。情報の利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当社は一切の責任を負いません。本記事に掲載の提供情報は、法的アドバイスの提供を目的としたものではありません。

葬儀の流れ
お通夜の時間・流れの解説!始まりから終わりまで

葬儀の流れ
お通夜の流れを把握しよう!準備から通夜ぶるまいまで

葬儀の流れ
参列者のお通夜の当日の流れは?お悔やみの言葉・注意点・マナーを解説

葬儀の流れ
病院で亡くなったらどうなる?逝去からお葬式までの流れを解説

葬儀の流れ
親が亡くなった時の手続きは?時系列ごとに詳しく解説

通夜の流れ | 一般的な葬儀の場合

自殺された方の葬儀や手続き

枕経とは?依頼の仕方や流れ、お布施の相場など

副葬品と棺に入れるもの・入れてはいけないもの

夜中にお亡くなりになった場合のお通夜はいつ?日程を決めるポイントを解説

逆さ水とは?故人の湯灌でも使われる?
横にスクロールできます

お葬式における接待係の役割とは? 接待係は何をすればいいのか
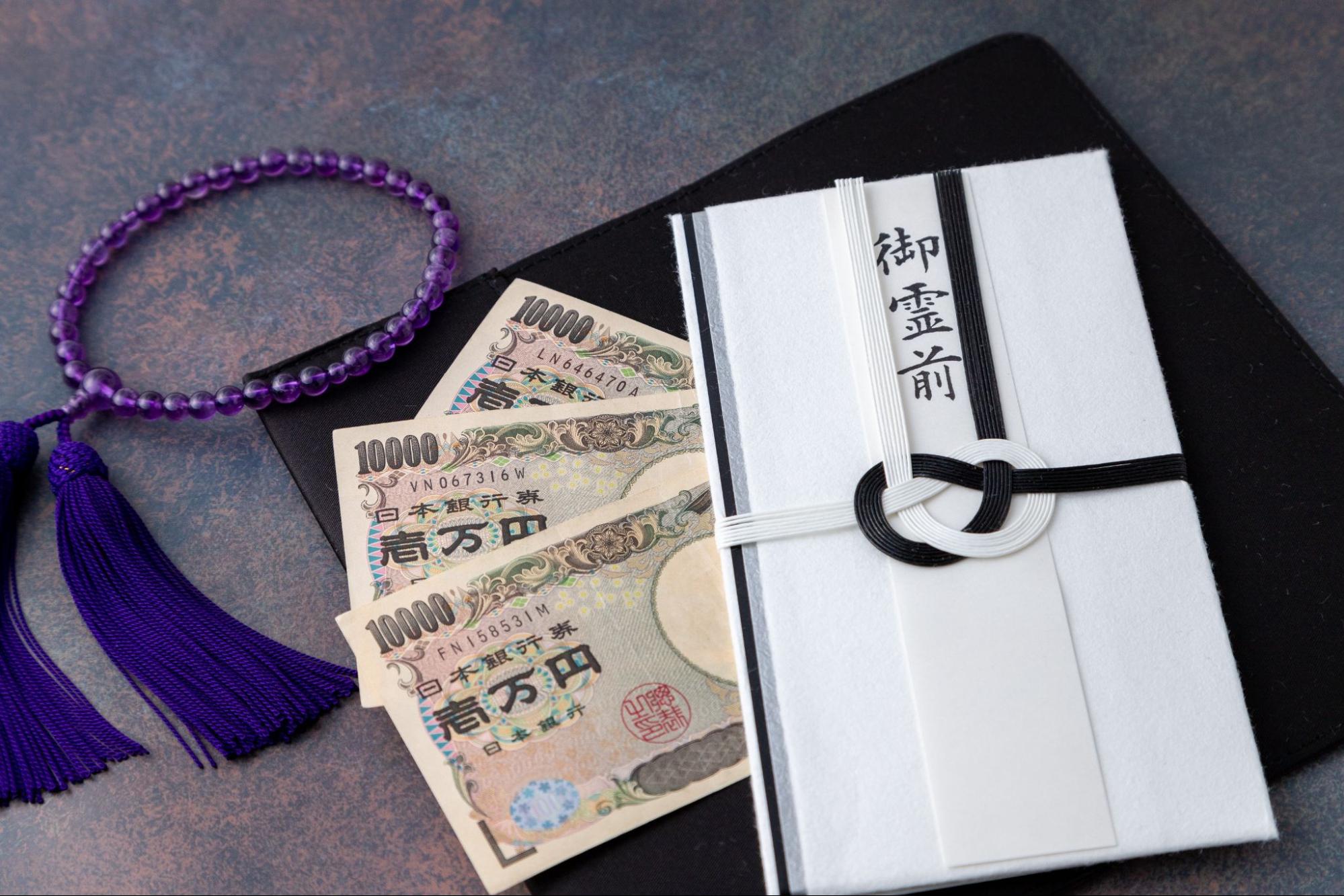
お葬式における会計係の役割とは?会計係は何をすればいいのか

お葬式の主な流れ!式前・当日・式後のスケジュールや日程を解説

「精進落とし」とは何をする?当日の流れと挨拶などやるべきこと

葬儀の日程を決める方法は?日程を決める際のポイントや注意点を解説

告別式にかかる時間は?流れとタイムスケジュールを解説
横にスクロールできます

全国 ︎5,000以上の提携葬儀場からご希望にあったお近くの葬儀場をご提案します。
